2025年4月29日
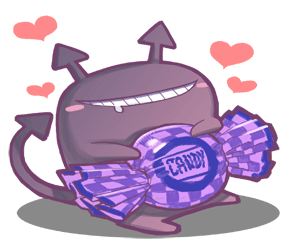
一見すると歯周病と糖尿病には関連がないように感じますが、最近の研究では、密接な関係性が示唆され始めているのです。
今回は、歯周病と糖尿病がどのように相互に影響し合うのか、そのメカニズムを解説していきます🦷
また、糖尿病患者が口腔ケアや生活習慣の改善によって、どのような効果が期待できるのかもご紹介します。
歯周病と糖尿病の因果関係とは?
日本歯周病学会から、歯周病の進行が糖尿病の血糖コントロールを悪化させる可能性があると示唆されました。
また、米国疾病予防管理センター(CDC)の報告によると、歯周病と糖尿病は相互に影響し合う関係で、一方が進行することで他方も悪化する可能性があると言われています。
このように、歯周病と糖尿病の関係性は深く、歯周病を予防することが糖尿病の予防にも繋がることが分かります。
相互に影響し合う具体的な症例
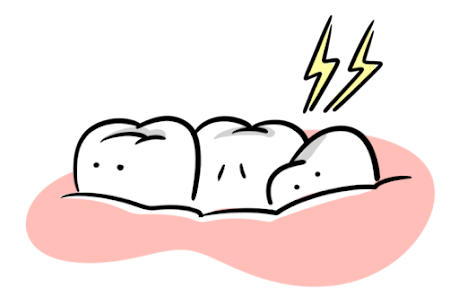
歯周病と糖尿病が相互に影響し合うことで具体的にどのような症状が出てくるのでしょうか。
1. 歯周病になると歯が抜ける
歯周用が進行すると、歯を支える組織が破壊され、最終的に歯が抜けるところまで悪化します。
歯がなくなってしまうと・・・
▹歯の噛み合わせが悪くなる
▹噛む圧力が弱くなる
▹痛みなどで噛めない
という状態になってしまいます。
2. 柔らかい炭水化物を好んで食べるようになる
歯が抜けてなくなると、うまく噛めなくなることから、比較的柔らかい食材を重点的に摂取するようになります。
柔らかい食材には、炭水化物を多く含んでいる傾向があります。
そのような食材を好むようになれば、糖質過多になり、糖尿病のリスクも高まってくるでしょう。
タンパク質や脂質を含むお肉屋お魚などは、歯がない状態で摂取するのは困難です。
3. 免疫や炎症の関係で歯周病が悪化
糖尿病が進行すると、免疫機能の低下や体内炎症が増加していきます。
免疫機能が低下すると、歯周病菌などに対する抵抗力が弱まることが報告されています。
つまり、糖尿病になると健康的な人に比べて歯周病のリスクが高まるのです。
「甘いものは虫歯や歯周病になりやすい」と言われるように、糖質という栄養素が関係している点は、糖尿病と同じです。
栄養素の観点からも、相互に影響し合うと言えるでしょう。
4. 糖尿病になると口が渇きやすくなる
糖尿病になると、高血糖になるので脱水症状が起こりやすく、唾液の分泌量が減少します。
そのため、口が渇きやすくなるのです。
唾液の分泌量が減ると、口腔内の自浄作用が低下するため、プラークや歯石も蓄積しやすくなります。
このような意味合いでも、歯周病と糖尿病は関係性が深いと言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか。
糖尿病が進行すると血糖コントロールが悪化し、唾液の分泌量や免疫力などの影響で歯周病の悪化にも起因します。
歯周病と糖尿病のリスクを軽減されるためにも、適切な口腔ケアや生活習慣の改善、バランスの良い食事を心がけるましょう😊






