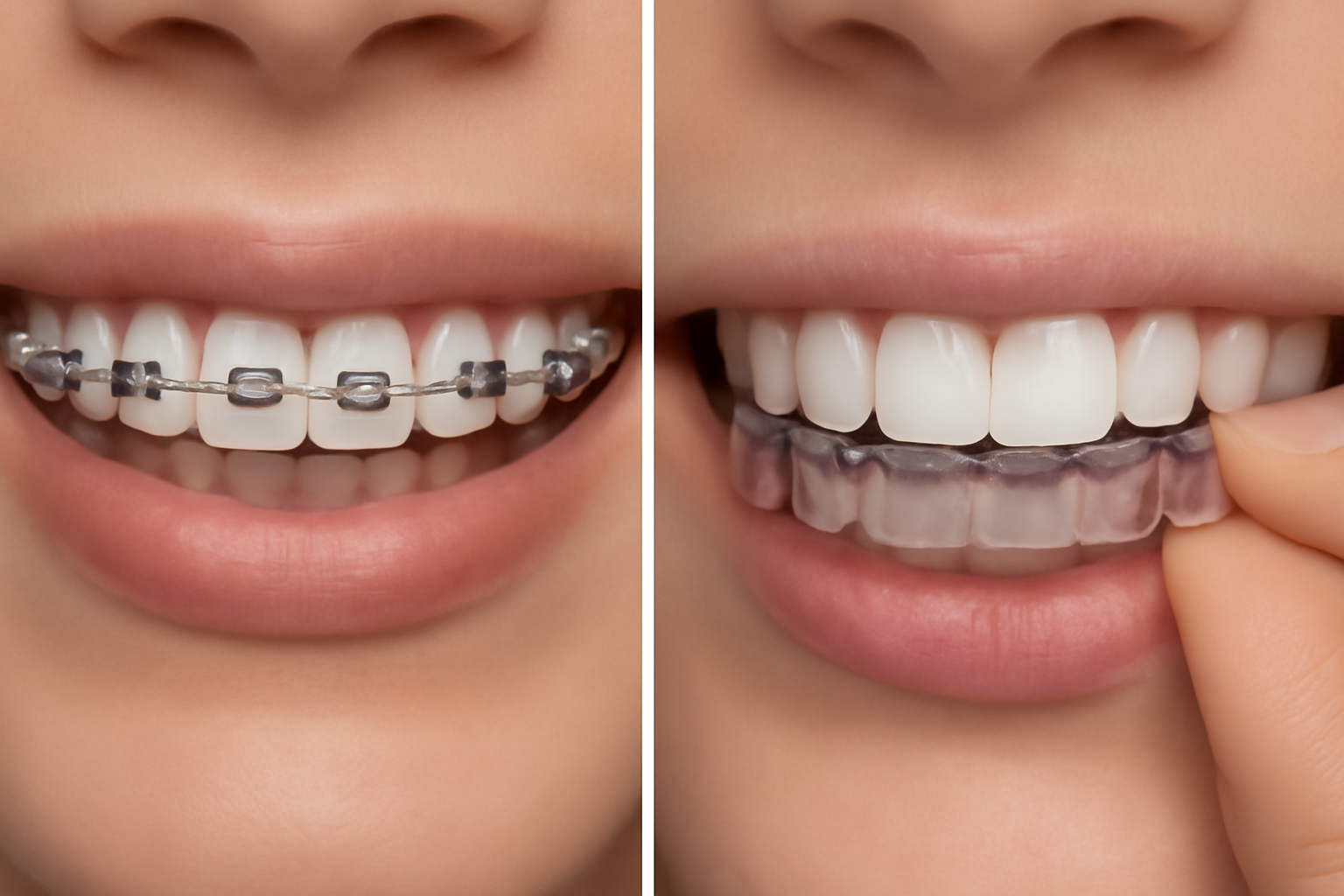2025年11月19日

(院長の徒然コラム)

はじめに
近年、デジタル技術の進歩は歯科医療の現場に革新をもたらしており、その中でも特に注目されているのが3Dプリント技術です。
とりわけ、義歯製作においては、人手や手間があまりかからず、効率性が良いことから、外国の歯科診療所で導入が進んでいました。
この度2025年12月より、ついに3Dプリントを用いた総義歯の保険適用が国によって認められることとなり、これにより義歯製作のコスト低減と患者の負担軽減が期待されています。
今回のコラムでは、3Dプリント総義歯の技術的側面、臨床的メリット・デメリットについて説明してみようと思います。
3Dプリント総義歯の概要
3Dプリント(積層造形)は、デジタル設計データに基づき、材料を層状に積み重ねて立体物を製作する技術です。
従来の総義歯製作は手作業と時間を要し、個々の患者に合わせたフィット性や機能性の調整には熟練した技術と熟練度が求められていました。
これに対し、デジタルスキャンとCAD(Computer-Aided Design)を併用することで、義歯の設計と製作の精度向上、効率化が可能となりました。
保険適用の内容とポイント
日本において、2025年12月から始まる保険適用は、従来の伝統的手法に比べてコスト効率の良い3Dプリント総義歯の技術を安定的にサポートすることとなります。
具体的には、口腔内スキャナーでデジタル印象を取得し、そのデータを用いて義歯をCAD設計、3Dプリントによる製作を行う流れになります。
今回、承認された材料とその価格は以下の通りです。
⚫︎歯冠部分の材料(商品名:ディーマ プリント デンチャー ティース)
→価格:1歯あたり59円
⚫︎義歯床部分の材料(商品名:ディーマ プリント デンチャー ベース)
→価格:1顎あたり2,026円
また、3Dプリントによる義歯の製作にかかる技術料については、標準の点数を用いて計算されます(点数:2,420点)。
ただし、適用を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
①歯科補綴治療に関して、専門知識と3年以上の経験を持つ歯科医師が1名以上勤務していること。
②次のいずれかを満たしていること:
・保険医療機関内に液槽光重合方式の3Dプリント義歯製作装置が設置され、歯科技工士がいる。
・もしくは、この装置を設置している歯科技工所と連携している。
この制度により、従来のアナログ工程と比べて製作時間の短縮とコスト削減が見込まれ、患者の待ち時間や経済的負担の軽減に寄与すると考えられています。
適用条件と各種規定
保険適用となるのは、原則として以下の条件を満たした患者です。
①口腔内の全ての歯を欠損している場合の総義歯(つまり上下顎同時に作れということ)
②既存の義歯が破損または適合不良で更新が必要な場合
③口腔・顎の状態が一定の改善目的に合致している場合
また、3Dプリント義歯の材料や製作工程に関しても、厚生労働省や保険研究機関のガイドラインに沿った規格に適合した製品の使用が求められています。
費用負担と診療報酬の詳細
従来の総義歯製作に比べて、3Dプリント義歯の導入にはコスト面でのメリットが大きいです。
具体的には、保険給付による自己負担額は次の通りになると思われます。
⚫︎診療報酬点数
従来の義歯に比べて、技工料や材料費のコストカットにより、総額で2割程度の減少が見込まれます。
⚫︎実際のコスト比較とメリット
従来法の義歯と比較した場合、以下のようなコスト面のメリットが明確になります。
①製作期間の短縮による治療費用の圧縮
②人件費や材料費の削減により、技工所やクリニック全体のコストが低減
③調整・再作成回数の減少**により、患者の通院回数と費用負担が減少
3Dプリント総義歯の臨床的メリット
①高精度な適合性と再現性
従来の総義歯は、模型や手作業による調整に依存するため、個々の患者の口腔粘膜や歯槽骨の微妙な変化に対応しきれない場合もありましたし、歯科技工士さんの技量にも左右されるところが多分にありました。
一方、3DスキャンとCAD設計は、極めて高い精度で歯列や顎の形態を再現可能であるために多くの臨床研究では、3Dプリント義歯は従来法に比べて適合性に有意さはないと報告されており、これにより患者の不快感や調整回数の削減に寄与しています。
(ただし機能印象ができていないという懸念はある)
②製作時間の短縮と工程の効率化
従来の義歯製作には、模造模型作製、歯科技工士さんによる調整、鋳造や樹脂重合といった複雑な手順を要しました。
これに対して、デジタルデータの取り込みと3Dプリントは、これらの工程を大幅に短縮し、通常1〜2週間かかっていた製作期間を1週間未満に短縮できるケースも報告されています。
③コストの削減と一貫性の向上
3Dプリントを用いた総義歯の最大のメリットの一つは、コストの削減と製作の一貫性の向上です。
従来の義歯製作では、多くの工程が手作業やアナログ工程に依存しており、その都度技工士の熟練度や経験に左右される部分がありました。そのため、同じ設計を再現し続けることや、多数の義歯を安定して作製するのは難しかったのです。
一方、デジタル設計と3Dプリントの導入により、義歯の形状やフィット性を数値化して保存・再現できるため、同じ設計を複数回再現することが可能となります。
これにより、一貫した品質の義歯を安定的に供給できるだけでなく、従来よりも材料や工程にかかるコストを抑えることができます。
また、世の中に広まることで大量生産や標準化が促進されることで、全体のコスト低減が期待されています。
④製作工程の合理化と時間短縮
伝統的には、義歯製作においては口腔内模型の採取、模型上での調整、鋳造や樹脂重合といった多くの工程が必要でした。
これらは時間と手間がかかり、特に調整段階では患者と歯科医師、歯科医師と歯科技工士の間で多くのやり取りが必要となっていました。
3Dプリントでは、口腔内スキャナーを利用したデジタル印象により、模型の物理的な採取工程を省略できるほか、設計もCADソフトウェア上で正確に行われるため、調整回数や修正時間を大幅に削減できます。
結果として、義歯の完成までにかかる期間は従来の半分以下になり、患者満足度の向上につながる可能性を示しています。
3Dプリント総義歯の臨床的デメリットと課題
一方で、3Dプリント義歯の普及に伴い、いくつかの課題も指摘されています。
①材料の耐久性と長期安定性の課題
現時点で使用されている3Dプリント用の材料の多くは、従来の樹脂や鋳造材料と比較して耐久性に劣ると報告されています。
特に、咀嚼負荷や口腔内の湿気・pH変動に対して長期的に安定であることを示す臨床データは限られており、長期的な使用においては材料の選択と改良とデータの蓄積が必要となります。
②適合性と微調整の必要性
高度なデジタル化により適合性は向上しているものの、実際の口腔は個々の微細な形態や軟組織の状態によって微調整が必要な場合が多いのです。
特に、義歯の縁や適合部位の微調整は、最終的には従来と同様に経験ある歯科技工士と、口腔内では歯科医師による調整が不可欠となるケースが多いです。
③コスト面と技術の普及
現在保険で認められている材料の3Dスキャナーやプリンターそのもののコスト、そして専用材料の価格も高めであるため、 歯科医院及び歯科技工所での導入コストのハードルが存在しています。
しかしながら、これらの設備や材料の普及とともに価格は低下傾向にあり、今後の普及促進が期待されています。
歯科医師及び歯科技工士の教育とノウハウの蓄積の課題
3Dプリント総義歯の普及に伴い、歯科技工士や歯科医師に求められる知識・技術も大きく変化してきております。
従来の手作業中心の技工法から、デジタル設計やプリント技術を使いこなすための教育訓練が必要となります。
このため、専門的な研修やセミナー、教育プログラムの整備が急務となっています。
また、各診療所や技工所間でのノウハウ共有や標準化も進められていますが、まだ十分に確立されていない部分も多いのです。
このため、個別の技術者や歯科医師の経験に依存する部分が未だ残りやすく、品質や適合性のばらつきが発生するリスクも存在ぢます。
今後は、より体系的で標準化された教育・研修制度の確立が、長期的な技術の安定供給と向上には不可欠です。
今後の展望
3Dプリント義歯の導入は、今後の歯科医療に多くの革新をもたらす可能性を秘めている。特に、以下のような展望が期待されています。
①素材の多様化と性能向上
より耐久性や生体適合性に優れた新素材の開発・普及により、長期使用に耐える高品質な義歯が作製可能となっていきます。
②技術の標準化と普及促進
3D技術による補綴物の、国内外の標準化団体や臨床ガイドラインの整備により、技術の精度と品質管理が向上し、医療従事者の技術の安定化が進んでいくことでしょう。
③カスタマイズ性の向上
患者一人ひとりの口腔内に最適化された義歯設計が可能となり、の向上につながるでしょう。
今後の課題
しかしながら、現在もいくつかの課題が残っている。
①長期的な臨床成績の蓄積不足
3Dプリント義歯の長期的な耐久性や適合性に関する大量の臨床データの蓄積がまだまだ必要です。
②材料コストとコストパフォーマンスのさらなる向上
導入コストの低減とともに、材料の価格と性能のバランスを取ることが求められます。
③法的・社会的な枠組みの整備
保険制度や規制の整備も重要であり、今後の政策展開を注視する必要があります。
歯科医師に読んで欲しい3Dプリント義歯の利点
①複数の義歯床や人工歯を一度に造形できるため、製作効率が高いです。
②臨床研究では、患者満足度やチェアタイムにおいて従来法とほぼ同等の結果が得られています。
(例として、Al-Kaffらの研究では、3Dプリント義歯は従来法に比べて義歯調整時間が短く、咬合調整時間が長い傾向にあることが示されている。 )
③3Dプリント義歯はミルド義歯や従来法よりも適合精度が高く、アンダーカットを含む複雑な顎堤形態への適応性も優れています。
(Hwangらの研究より)
歯科医師に読んで欲しい3Dプリント義歯の欠点
①人工歯の審美性の低さ
人工歯用の光硬化性脂はモノリシック構造であるため、多層構造の既製人工歯に比べて審美性に劣ります。
②機械的性質と長期安定性の問題
3Dプリント義歯に使用される材料の機械的物性や長期的な安定性は従来法やミルド義歯の義歯床材料に比べて劣ると指摘されています。
また短期間使用例での破折も報告されています。
③リライニングの接着強度の弱さ
in vitro研究によると、リライニング材との接着強さは従来法やミルド(ミリング)義歯と比較して弱い傾向があり、臨床使用においても問題となる可能性があります。同時に義歯修理時の材料接着性も従来より劣るということです。
義歯用3Dプリント光硬化性脂の改良と今後の可能性
近年、義歯用の3Dプリント光硬化性脂の低機械的物性を改善するために、補強材(フィラー)の添加が有効であることが研究で示されています。
東京医科歯科大学はセルロースナノファイバー(CNF)を低コストかつ生体適合性の高い素材として選び、義歯用光硬化性脂に添加した結果、0.5wt%のCNF添加で曲げ強度が約46%向上したと報告しています。
また、従来の義歯床用レジンと比較すると、3Dプリント光硬化性脂は色差が大きく、着色しやすい特性がある。
CNFの添加量が増えるほど色相の安定性が向上し、色差の低減に寄与することが示されています。
これにより、CNF添加は環境負荷の少ない軽量素材として、補強効果も期待できる新たな義歯床用材料の発展に寄与するかもしれません。
終わりに
日本における3Dプリント総義歯の保険適用開始は、歯科医療の質の向上と患者負担の軽減に大きく寄与する画期的な出来事です。
高精度・高効率な製作ができるこの技術は、適合性や再現性の改善、工期の短縮とコスト削減など多くのメリットをもたらします。
一方で、材料の耐久性や長期臨床成績、技術者の教育といった課題も抱えています。
今後、更なる技術革新と臨床研究の積み重ねにより、3Dプリント総義歯はより安定した基盤のもと、一般臨床においても標準的な治療選択肢となることが期待されます。
歯科界全体での協力と努力が、より良い義歯提供を実現し、患者一人ひとりの生活の質の向上につながることを期待せずにはいられません。