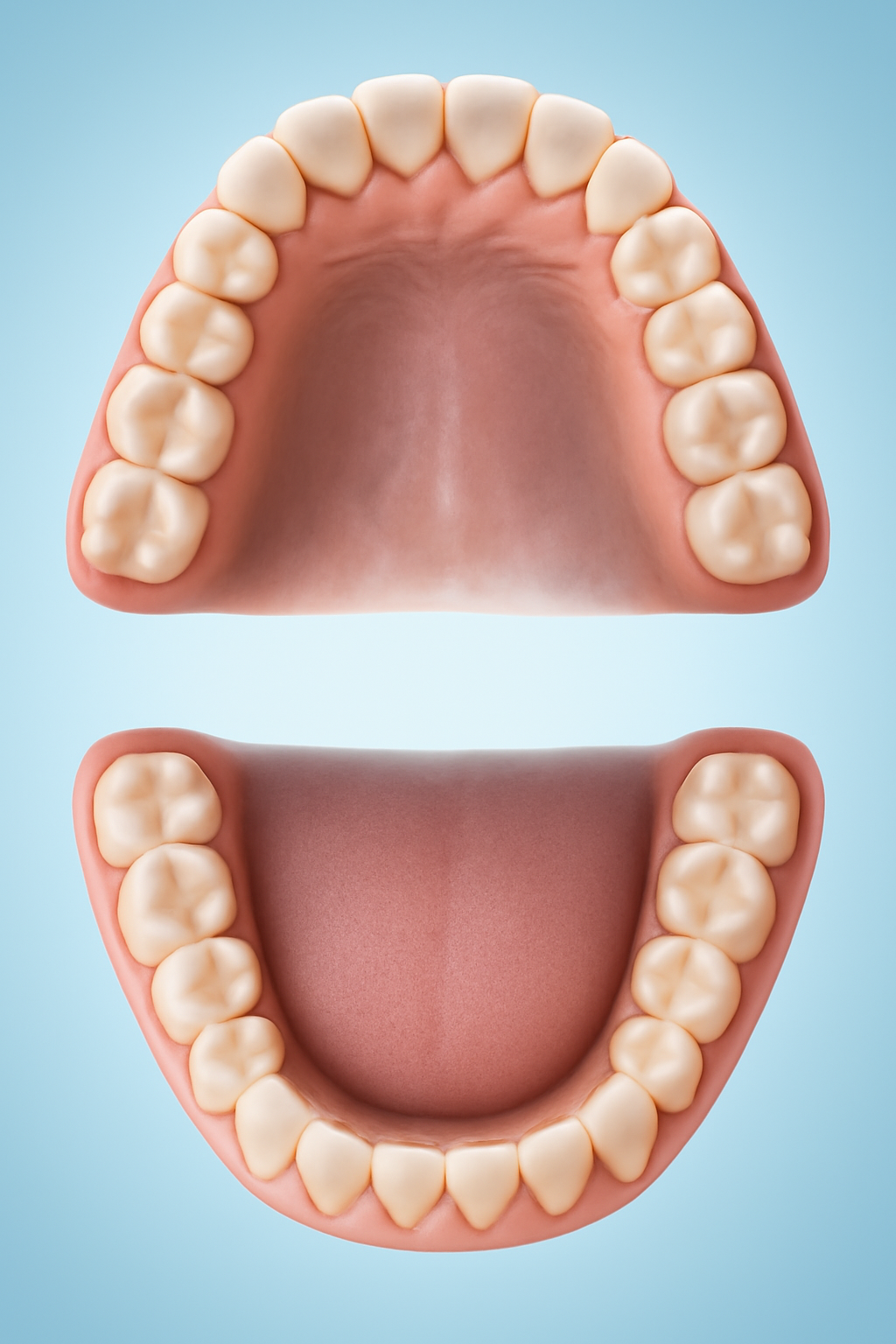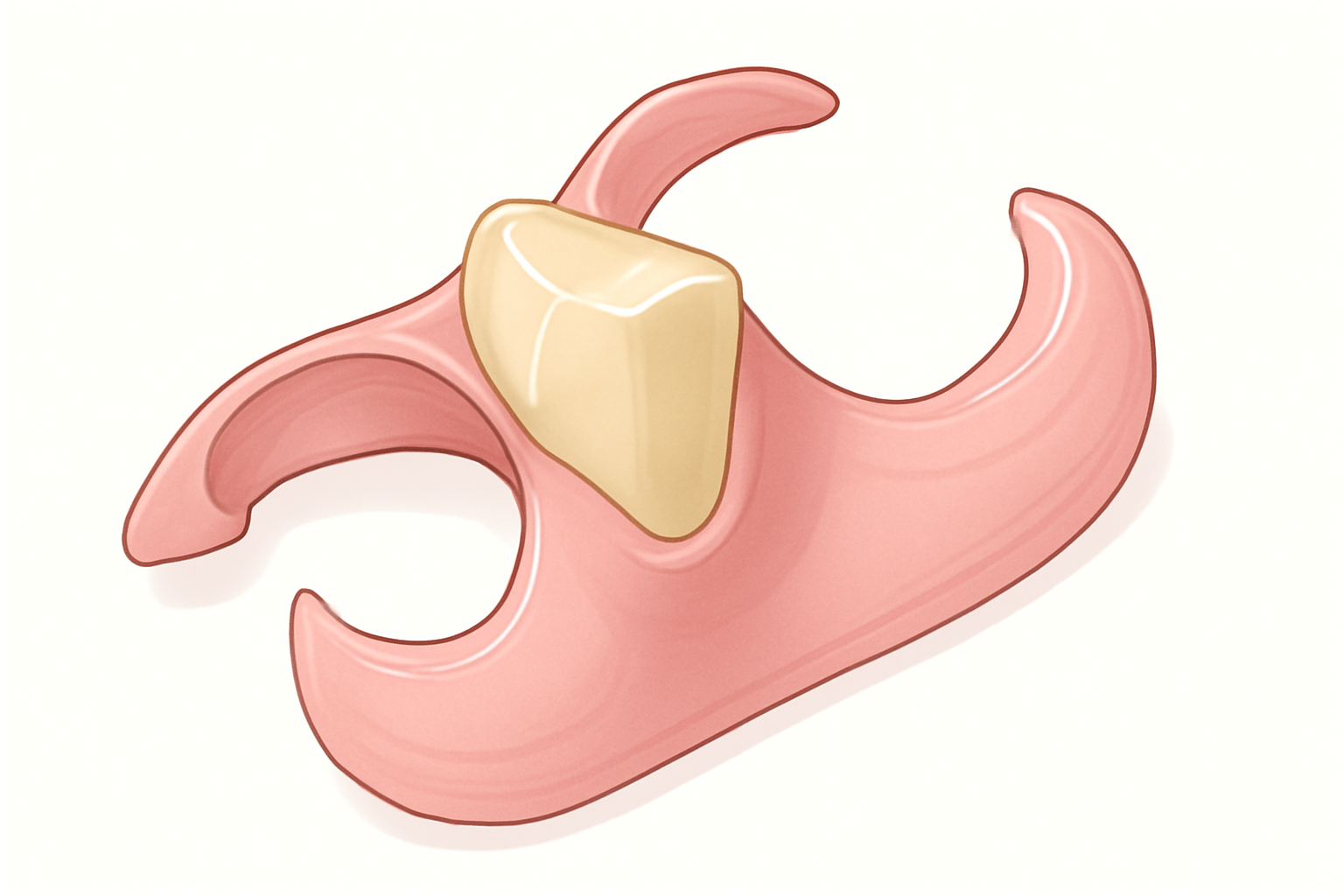2025年5月18日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
歯科医療はこれまで、肉眼や二次元画像(通常のデンタルエックス線写真やパノラマエックス線写真)を主な診断ツールとして診療を進めてきました。
これらの画像診断は、多くの臨床場面で有効ですが、構造物の重なりや平面像により、微細な病変や複雑な解剖学的関係を正確に把握することが難しい場合もあります。
しかし、近年の画像診断技術の進歩により、立体的かつ高解像度な三次元画像の取得が可能となり、歯科診療の精度向上に貢献しています。
その中心的存在が、「歯科用コーンビームCT(CBCT)」です。本コラムでは、「ロ腔(根管や歯周組織が存在する歯槽骨や周囲構造)」の状態把握において、なぜCBCTが欠かせない診断ツールとなり得るのか、その特徴、臨床応用、注意点について解説します。
なお、今回はかなり専門職向けの内容となっています。医療従事者向けに書いていますのでご了承ください。
歯科用CBCTの歴史と技術背景
⚫︎画像診断の発展
歯科分野の画像解析という分野は急速に発展してきました。
1895年、レントゲン博士によりエックス線が発見された翌年には、歯のエックス線写真が撮影されています。
1900年には現在の二等分法の原型を用いた根管充填の適不適が判断されています。
その後,1931年に頭部エックス線規格撮影(セファログラム)が、1949年にパノラマエックス線撮影装置が開発されている。
⚫︎CT(Computed Tomography)の登場と歯科への応用
1972年にCormack博士とHounsfieldらによる全身用CTの開発により、体内の立体構造を高精細かつ非侵襲的に画像化できる手法が確立されました。
この技術は医科だけでなく歯科医療にも応用されたものの、この時代のCTの大きな装置は局所的な部位を扱う歯科領域には適さず、歯科用に特化した小型の装置開発が求められました。
⚫︎歯科用コーンビームCT(CBCT)の発展
1990年代に日本大学の新井先生がパノラマエックス線写真装置を改良し、解像度が高く歯や歯周組織を三次元的に詳細に描出可能な装置の開発を試み、その結果製作されたものが今回の題目である歯科用コーンビーム(CB)CTなのです。
目的は「高解像度・低被ばく・小型・迅速」モデルの実現でした。その結果、「歯科用コーンビームCT」が登場し、現在では歯や歯周組織の詳細な三次元画像が得られるようになりました。
歯科用CBCTの基本的特徴と性能
⚫︎高解像度と小型化
歯科用CBCTの解像度は2 line pair/mm以上が可能です。
これにより、歯根の微細構造や根管形態、骨折や病変の微細な変化も明瞭に捉えられるようになりました。
加えて、装置はコンパクトで設置場所の制約も少なく、診療所において容易に導入できるように発展していったのです。
⚫︎迅速な撮影と低被曝
今日のCBCTでは撮影時間は数秒程度(当院の最新機種で7.7秒)と短く、患者の負担も軽減されています。
被曝線量もパノラマ写真と同程度に抑制されているため、安全性も向上しています。
⚫︎3D画像と多角的評価
CBCTではスライス画像(断層像)だけでなく、直交する裁断面や三次元再構成画像も提供され、明暗・陰影だけに頼らず、構造の詳細な評価が可能となりました。
これにより病変などの見落としも減り、分析力も格段に向上したのです。
歯科用CBCTを使う上での基礎知識
歯科用CBCTは、2012年の時点で日本全体の約68,000軒の歯科医院のうち、1,000台を大きく超える数が導入されていると報告されています。最近では、パノラマX線撮影装置とのハイブリッドタイプなど、低価格の機種も登場し、今後さらに普及が進むことが予想されます。
そこで、歯科用CBCTに関連する重要な用語や知識について、以下に5つのポイントを挙げて説明します。
①スライス厚
スライス厚は、全身用CTの場合、X線ビームの厚みもしくは検出器の厚みを表す用語です。
歯科用CBCTの場合、厳密にはスライス厚という用語は存在しませんが、装置のパンフレット等に記載されている「スライス厚」は、実際にはボクセルの大きさを表しています。
②ピクセルとボクセル
じゃあボクセルとはなんぞやって思われますよね。それにはピクセルの説明から必要となります。
デジタル画像は小さな正方形(ピクセル)の集まりで構成されています。
歯科用CBCT装置では、最小のピクセルサイズが現在0.1×0.1mm程度です。
ボクセルは、このピクセルに厚みを加えた三次元の単位となります。
ピクセルやボクセルが小さいほど高解像度の画像が得られますが、ノイズも目立つようになるため、実際の臨床では対象や目的に応じて適切なサイズを選択する必要があります。
③CT値
CT値は、各組織のX線吸収値を水を基準(0)として数値化したものです。
しかし、歯科用CBCTでは散乱線の影響が強く、撮影領域も限定されるためCT値を正確に算出することは困難です。
そのため、歯科用CBCTは従来の歯科用X線写真やパノラマX線写真と同様に、コントラスト画像として扱われます。
④アーチファクト
歯科用CBCTで特に問題となるアーチファクトには、金属によるもの、体動によるもの、コーンビームによるもの、被写体の位置によるものなどがあります。
金属アーチファクトは日常の歯科臨床でほぼ必発するもので、金属周囲に顕著な低密度領域を生じさせ、誤った診断につながる可能性があります。
これを避けるためには、複数の断層像を比較し、視診や触診、従来の歯科用X線写真も参考にしながら総合的に判断することが重要です。
⑤裁断面
歯科用CBCTは三次元画像を様々な方向から観察できる利点があります。
一般的なaxial、coronal、sagittal画像に加え、歯列に沿った断面(パノラマ様断面)や、歯軸に垂直な断面(クロスセクション)なども利用できます。
適切な裁断面を選択することで、病変の立体的な把握が可能となります。
臨床におけるCBCTの意義と応用範囲
⚫︎根管治療(歯内治療)の高精度化
歯科用コーンビームCT(CBCT)は、根管治療の分野において革命的な影響をもたらしました。従来の二次元画像では捉えづらかった複雑な根管系の詳細、追加の根管の有無、根尖病変の正確な位置や大きさを三次元的に評価可能です。
これにより、根管治療の精度が向上し、再治療の際も効果的な計画が立てられるようになりました。
⚫︎歯周組織疾患の診断と評価
歯科用CBCTは、歯周病の診断や骨吸収の評価においても非常に有効です。
従来の二次元画像では、骨吸收の範囲や骨質の状態を立体的に把握することは難しかったですが、CBCTでは、歯槽骨の骨密度や瘢痕形成、骨の垂直的な吸収状態、骨量の変化を三次元的に正確に評価できます。
これにより、重度の歯周病患者の治療計画や、骨移植や再生療法の適否判断にも役立ちます。
特に、部分的に骨吸収が進んだ患者や、外科的治療を併用する必要性が高い症例では、より正確な診断が治療の成功率向上に寄与する。
実際当院で歯周外科を行う場合は、前後でCBCTによる確認を行っています。
⚫︎インプラント治療前後の詳細評価
インプラント治療においては、骨の質・量を詳細に把握することが極めて重要です。
歯科用CBCTは、骨の高さ・幅だけでなく、頬舌方向や上下方向の骨量も正確に評価できるため、インプラントの予備的評価に最適です。
また、手術前の骨の位置や神経管・上顎洞との距離測定、埋伏歯の位置把握、手術後の骨癒合や腫瘍・骨折の経過観察に活用できます。
⚫︎埋伏歯やインプラント手術の計画
埋伏歯やインプラントを安全に手術するためには、その解剖学的関係を詳細に理解する必要があります。
CBCTにより、埋伏歯の頬舌的・上下的な位置関係、周囲の血管や神経の位置を正確に把握できるので、術中の合併症リスクを大きく低減できるのです。
この情報を基に、最適な手術計画や予想される困難点を事前に洗い出し、より安全かつ効率的な治療を行うことができます。
⚫︎顎顔面の複雑な解剖の評価
埋伏歯や顎顔面の複雑な解剖を三次元的に把握することは、外科的介入や矯正治療の重要なステップです。
CBCTを用いることで、患者個々の解剖学的特徴を理解し、安全で効果的な治療を実現できます。
具体的な歯科用CBCTの臨床応用の際の有効性と注意点
歯科用CBCT(コーンビームCT)は、歯科診療において革新的な画像診断ツールとして台頭しています。特に根管治療やインプラント、口腔外科領域での積極的な活用が進んでいます。
その有効性と留意すべきポイントについて解説します。
1. 歯髄・歯周疾患に対する有効性と注意点
歯科用CBCTは、根管内の複雑な構造や骨病変の詳細な把握に優れ、従来のレントゲンや歯科用顕微鏡では難しかった情報を提供します。
例えば、難治性の根尖性歯周炎では、CBCTにより根分岐部から頬側へ広がる骨吸収が明瞭に観察でき、治療計画の精度向上に寄与します。
また、術前だけでなく、術中・術後の組織の創傷治癒や再生状態も詳しく評価できます。
ただし、アーチファクトや検出限界といった制約も存在し、これらを理解した上で適切に使用する必要があります。
2. 小児歯科領域での有効性と注意点
小児症例では、過剰埋伏歯や萌出異常の評価にCBCTが役立ちます。(というかそれがほぼ全て)
立体的画像により、歯の位置関係や根の形成状態、近接する構造物との距離を詳細に把握できるため、早期の治療判断や抜歯のタイミングに大きく寄与します。
ただし、被ばくリスクを考慮し、3歳以上の協力が得られる患者に限定されることが多く、低年齢では全身用CTの併用や、必要に応じて慎重な判断が求められます。
(まあそもそも背が足りずに機種によっては取れないケースも多いですが)
3. インプラント治療に対する有効性と留意点
インプラント埋入前の診断には、骨の状態や解剖学的構造の詳細把握が不可欠です。
CBCTは、上顎洞、神経管、骨密度の評価に有効であり、コンピューターガイデッドサージェリーにも活用されます。
ただし、骨質や密度の正確な評価にはMDCT(全身の医科CT)に劣る点も念頭に置き、局所の状態に合わせて適切な画像診断を選択すべきです。
4. 口腔外科疾患に対する有効性と注意点
顎変形症や外傷、腫瘍性疾患など多くの口腔外科疾患において、CBCTは硬組織の詳細な三次元画像を提供します。
一方、軟組織や血管・リンパ節の評価には向かず、そのため疾患の性質に応じて全身用MDCTの利用も検討されます。特に腫瘍や粘膜の浸潤状況など、軟組織の詳細は他の画像検査に頼る必要があります。
このように、歯科用CBCTは特定の診療分野で大きな効果を発揮していますが、その特性や制約も理解した上で適切に活用することが重要です。
将来的には、画像技術の進歩とともに、より多くの診療において有効性が拡大していくことが期待されます。
ですが、現時点の性能では「軟組織の質的分析はできない」ということを頭に入れておく必要があります。
CBCT画像の解釈と診断のポイント
⚫︎適切な裁断面の選択
CBCT画像は、単一の断層や3D再構成画像だけでなく、患者の解剖学的構造に応じた最適な裁断面を選択することが重要です。
たとえば、根管や骨折の評価には、縦断・横断・斜位の調整を行い、解剖構造のゆがみや重なりを避ける必要があります。
⚫︎アーチファクトの識別と対処
金属アーチファクトや動画像によるブレ、コーンビームコロケーションによる歪みを理解し、正確な診断の妨げとならないよう注意が必要です。
複数の断層像を比較したり、他の画像補助と併用したりすることも有効です。
⚫︎軟組織の評価には注意
前述の通り、CBCTは硬組織の描出に優れていますが、軟組織のコントラストは低く、病変の質的診断には適さない場合もあります。
そのため、軟組織疾患が疑われ、かつ精査が必要と判断した場合は、大人しく紹介してMRIや全身用CTの併用を検討しましょう。
CBCT導入における運用と注意点
⚫︎適切な撮影範囲と頻度
歯科用CBCTの臨床利用においては、必要最小限の撮影範囲に留めることが重要です。
ヨーロッパ顎顔面放射線学会(EDMFR)のガイドラインでも、歯科用CBCTの使用に関して基本原則を定めています。
それによると、CBCTの過剰な範囲や頻度の撮影は、患者の被曝リスクを増やすだけでなく、過剰診断や誤診を誘発する可能性もあります。
具体的には、状況に応じた明確な理由と臨床判断に基づき、ポイントを絞った撮影を心がけることが推奨されます。
例えば、埋伏歯の位置確認や根管の詳細観察には狭い範囲のCBCTを用い、原則として必要な情報だけを撮影します。
また、定期的な経過観察や治療効果の評価においても、再撮影は最小限にとどめ、以前の画像と比較しながら変化を慎重に評価することが求められます。
⚫︎放射線防護と患者への説明
CBCTを導入する歯科医師およびスタッフは、放射線防護の観点から十分な知識と訓練を受ける必要があります。
適切な防護具の使用や、撮影範囲・方法の最適化に努めることが、患者安全の基本です。
さらに、患者へは撮影の目的、必要性、リスクについて丁寧に説明し、納得のうえでの同意を得ることが倫理的かつ法律的にも求められます。
撮影前には、患者の体調や妊娠の有無も確認し、安全性を最優先に対応します。
CBCT画像の正しい解釈と臨床判断のポイント
⚫︎画像解釈の基本
CBCT画像を読む際は、まず断層画像を複数の視点から観察し、解剖構造の正確な位置や形態、病変の範囲と性質を把握します。特に、以下のポイントに注意しましょう。
①根尖部の状態
根尖病巣や感染の有無、破折の有無のチェック
②骨吸収の範囲と形態
歯周病や腫瘍の浸潤範囲のチェック
③血管・神経の経路
インプラントや外科手術の安全域の把握
④金属アーチファクトの影響
診断に与える影響を理解したうえで補助的に他の画像や診査結果も考慮して診断していく。
⚫︎裁断面と3D再構成の活用
適切な裁断面の選択と、多角的な観察は、完全な診断を導くために重要です。
根管や骨折、骨吸収の詳細評価には、縦断面や横断面だけでなく、3D再構成画像も併用し、立体的な理解を深めましょう。
⚫︎誤解と見落としをしない診断
CBCT画像にはアーチファクトや限界も存在します。
金属アーチファクトによる偽の病変や、他の障害(例:患者の体動など)によるノイズには注意が必要です。
診断には補助的に臨床所見や伝統的画像を併用し、総合的な判断を心がけましょう。
今後のCBCTの未来
CBCT技術は、今後も進化を続け、より高解像度で低被爆の装置が登場すると期待されています。
また、画像解析AIの導入により、診断の正確性や効率性も向上していく見込みです。
このような進展により、歯科医師はより正確で早期の診断を行い、患者一人一人に最適な治療計画を立てることが可能となるでしょう。
また、価格の低下や撮影時間の低下、小型化も進み、導入できる歯科医院も増えていくと予想されます。
終わりに
いかがでしたか?
歯科用コーンビームCT(CBCT)は、ロ腔や歯周組織、骨の三次元的な詳細評価において非常に有用なツールです。
従来の二次元画像では把握が難しい複雑な解剖学的構造や微細な病変も、高解像度のCBCT画像を通じて正確に捉えることが可能となりました。
これにより、診断の精度向上や治療計画の最適化、術前・術中・術後の見える化が実現し、患者の安全性や治療効率を高めています。
しかしながら、CBCTの導入にあたっては、適正な撮影範囲の設定や放射線被曝リスクの管理、画像解釈の技術と知識の向上が不可欠です。
特に、金属アーチファクトや動画像の影響を理解し、補助手段や多角的視点からの評価を行うことが、正確な診断を行ううえで重要です。
さらに、現在進行中の技術革新により、より高性能かつ低被ばくの装置や、AIを活用した画像解析システムの登場が見込まれています。
これにより、歯科医師はより早く正確な判断を下し、患者に最適な治療を提供できる未来が期待されます。
結論として、歯科用CBCTは、ロ腔の状態把握に不可欠な画像診断ツールであり、適切に運用・解釈することで、歯科治療の質と安全性の向上に大きく寄与します。
今後も技術の進歩とともに、その臨床応用範囲はさらに広がるとともに、我々歯科医師は最新の知識と技術を習得し続けることが求められます。