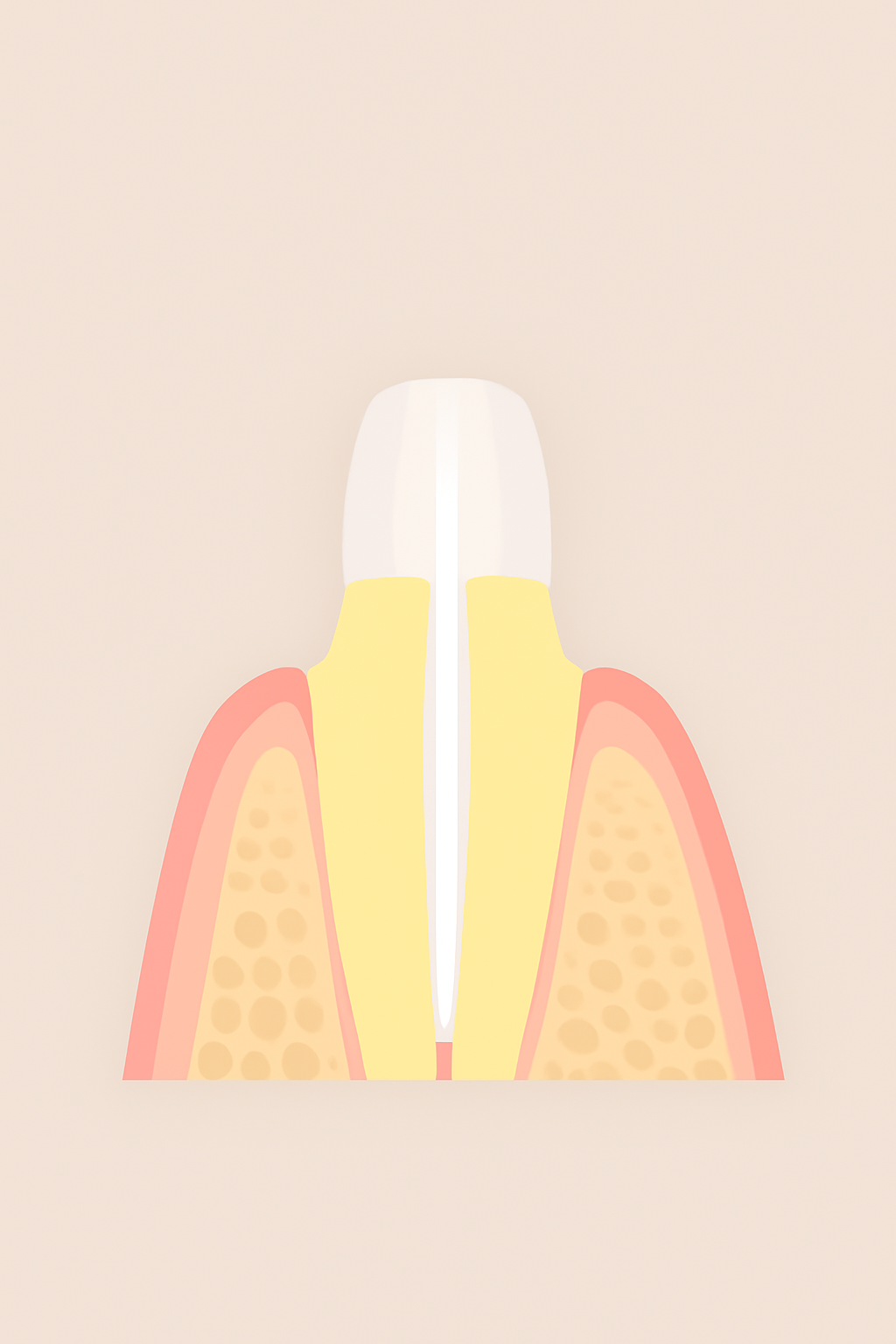2025年10月29日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
こんにちは。タイトルを見て二度見した方もいらっしゃるかもしれません。
昨日人間の歯の論文に読むことに疲れていたとき、Yahooの記事で犬のブラッシングに関する記事があり、何を血迷ったのか犬のブラッシングに関する論文データを漁るという暴挙に出ました。
今回は完全にバラエティー回です💦。
読んで得た知識を、アウトプットしていこうと思います。
人間も犬も一緒で、犬の健康維持においても口腔ケアは非常に重要です。
歯周病や歯肉炎、歯石の蓄積は、単なる口腔内の問題にとどまらず、心臓や肝臓、腎臓などの全身疾患に悪影響を及ぼすこともあります。
(これも人と一緒!)
特に中・高齢犬は適切なケアが習慣化されていないと、歯周組織の疾患や悪臭、痛みといった問題が長期的に進行する恐れがあります。
そこで、犬の口腔内を健康に保つためには、正しい歯磨き方法と適切な道具の選定、そして継続的なケアが不可欠です。
今回のバラエティーコラムでは、効果的な歯磨きの基本技術や新品種の歯ブラシの開発背景、実験結果、そして実際に行う際のポイントやコツを詳述し、飼い主の皆さまが安心して実践できる情報を提供するとともに、一緒に勉強していきましょう!
犬の口腔内の特徴と虫歯の少なさ、歯周病の多さ
人と比べて、イヌの口腔内は弱アルカリ性の環境にあります。
通常、ヒトの口腔内pHは6.5~7.0の弱酸性に対し、イヌの口腔内は8.5~9.0の弱アルカリ性です。
このため、虫歯は発生しにくいとされています。さらに、イヌには人のようにストレプトコッカス・ミュータンス(Streptococcus mutans)といった虫歯の原因菌がほとんど存在しません。
加えて、唾液にアミラーゼ酵素が少なく、デンプンの分解能力が低いため、糖質が口腔内に長く滞留しにくいことも虫歯の発生を抑える一因です。
さらに、臼歯の形態も犬の歯は平らで凹みが少なく、人の歯に比べると菌や歯垢の付着も少ないと考えられています。
(ここは本当に羨ましい!)
しかしながら、犬の口腔内には歯肉炎や歯周病の症例が多く見られます。
歯周病の原因は、多くの場合歯垢の蓄積です。歯垢は食べ残しや細菌の塊であり、放置されると石灰化し歯石へと進行します。
歯石は歯垢の蓄積を促進し、歯肉炎の原因となるだけでなく、歯槽骨の破壊や歯の喪失に至ることもあります。
さらに、歯周病が重症化すると、歯肉からの出血や痛みだけでなく、感染菌が血流を通じて全身に広がり、心臓や腎臓、肝臓の疾患を引き起こすケースもあります。
さらにさらに、歯医者でこの記事を読んでいる方ならピンと来たはずです。
「え?弱アルカリ性なら人のように歯の石灰化は起きやすいけど、歯石付きまくるんじゃね?」と…。
その通りなんです。
犬の口腔内は弱アルカリ性で歯石が付きやすい傾向があり、人よりも圧倒的に再石灰化と歯石がつきやすい傾向にあるんです。
虫歯になりにくいのは良いけども、歯石がつきやすく歯周病になりやすいのは嫌ですね…
犬の口腔衛生の重要性とリスク管理
犬の口腔環境に潜むリスクを理解し、適切な対策をとることは、犬の健康を維持し、長く快適に暮らすために重要なことです。
犬の口腔内には、常在菌としてCapnocytophaga spp.をはじめとする微生物が存在しています。
これらの菌は通常、健康な犬の口腔内では問題なく共存していますが、歯石や歯垢の蓄積が進むと、炎症や歯周病を引き起こす原因となります。
一方人においてもで、Capnocytophaga spp.は人にとっても重要な日和見感染菌であり、免疫力の低下した人が咬傷やひっかき傷から感染しやすく、重症化すれば敗血症や髄膜炎にまで至ることもあります。
(この菌は人の口腔内にもいるんです。)
日本国内では、イヌやネコの口腔内に高頻度で存在しており(保有率は90%以上)、感染例も報告されています。
そのため、犬の口腔内細菌を適切にコントロールすることは、公衆衛生上も非常に重要です。
この背景から、犬の口腔ケアの目的は、単に見た目や臭いの改善だけではなく、感染リスクを低減し、全身の健康を守ることにあります。
特に、歯垢や歯石の除去は、歯周病や歯肉炎の進行を抑えるとともに、菌の蔓延を防ぐ効果もあります。
市販のデンタルケア製品とその効果
さまざまな商品が市場に出ており、歯ブラシや歯みがきペースト、口腔シート、ガムなど、それぞれの特長を生かした商品が販売されています。
研究では、これらを使った各種の歯磨き方法の効果が比較されており、結果として、「直接的な歯磨き行為が最も除菌効果が高い」ことが明らかとなっています。
(これは人も同じですね。要するに機械的清掃が一番除菌効果高いってことです。)
具体的には、犬に対して歯ブラシやペースト、ジェル、歯みがきシートを用いて口腔内の細菌数を測定したところ、全ての方法で試行後の菌数が有意に減少していました。
特に、「歯ブラシ・ペースト」や「歯みがきシート」の方法は、菌数の低下率が高く、効果的な清掃を示しています。
しかしながら、「間接歯磨き法」と呼ばれる「歯みがきビスケット」や「歯磨きガム」のような商品は、歯垢や菌の除去効果が限定的です。
実験では、試行後に菌数が増加するケースもあり、これらはあくまで補助的な手段と位置付けられるべきだと考えられます。
(人でも同じで、例えば歯ブラシをせずにマウスウォッシュだけでは、除菌効果は不十分なのと同じです。)
歯磨きのコツと注意点
犬の口腔ケアを成功させるためには、いくつかのポイントがあります。
①適切な頻度とタイミング
理想的には毎日、できれば食後に行うのが望ましい。タイミングを決めておくと忘れずに続けられます。
犬が逃げる場合?…どうすれば良いんでしょう?獣医師さん教えてください。
②道具の選び方
犬の口の大きさや歯の形に合わせた歯ブラシを選び、毛先は柔らかく。ペーストやジェルは犬用の安全なものを使い、慣れさせるためにおやつやご褒美を併用。
(人の子供でも一緒です。小さい頃から動機づけが大事です。歯磨きをちゃんと習慣づけている子供は褒めてあげましょう。)
③持ち方と力加減
ペングリップが基本。まずは20g程度の軽い力から始め、慣れてきたら徐々に力を調整し、150g(人の歯を磨く理想の圧力)まで負荷をかけても問題ありません。
犬の部位別のケアのポイント
①臼歯(奥歯)の磨き方
奥歯は犬の口の中でも特に汚れやすく、磨き残しが生じやすい部分です。
上顎の前臼歯と後臼歯、下顎の前臼歯と後臼歯を順序よく丁寧に磨きましょう。
ポイント
⚫︎まずは犬が受け入れやすい上顎の奥歯から磨き始めると良いです。
⚫︎口を開けて奥歯を露出させるには、以下の方法を用います。
⬜︎方法1:額や頭に手を添え、親指を口角に少し入れる。
⬜︎方法2:マズル(目から鼻先、口の周りの部分)を包むように親指と人差し指で上の歯の後ろ側を優しく掴む。
上の臼歯は、口角を少し上げるようにして磨くと磨きやすいです。犬によっては嫌がる場合もあるので、無理のない範囲で丁寧に行ってください。
②切歯(前歯)の磨き方
切歯は犬の口の前部に位置し、小さく敏感なため、磨きにくい部分です。
汚れや歯垢がたまりやすく、特に歯と歯の隙間に食べかすや菌が詰まりやすいため、注意して磨きましょう。(これは人も同じです。)
ポイント
⚫︎上唇を持ち上げて、歯間のすき間を露出させましょう。
⚫︎縦にブラシを動かして汚れを掻き出す「縦磨き」を行いましょう。
⚫︎時間を短縮して効率的に行うために、片側ずつ上手に磨きましょう。
⚫︎上下の唇を同時に動かすもしくは手で持ち上げて、歯と歯間に残った汚れを除去しましょう。
③犬歯)の磨き方
犬歯は鋭く突き出した部分であり、ポイントとなるのは敏感さを考慮しつつ、しっかりと清掃しましょう。
ポイント
⚫︎犬の気持ちを尊重し、嫌がる場合は無理に長時間続けない。
⚫︎上唇や下唇を優しく持ち上げ、歯の見える状態にしてから磨きましょう。
⚫︎犬歯の縁や裏側も忘れずに磨きましょう。
歯みがきのポイントとコツ
①時間管理
特に敏感な犬は、長時間のブラッシングを嫌がることが多いです。
目安は1~2分以内に短時間で済ますことが理想です。(人間の半分)
②ポジティブな声がけとご褒美
好きなおやつや褒め言葉を併用し、歯みがきタイムを楽しい体験にしましょう。
③継続の重要性
毎日の習慣化が歯周病予防の最大のポイントです。無理なく続けられる環境づくりが成功の秘訣です。
まとめ:歯磨きは習慣と技術の積み重ね
犬の口腔衛生維持には、まずは正しい知識と基本動作の習得が不可欠です。
適切な道具とやさしい術式を用い、毎日コツコツと続けることが、病気の予防と健康の維持につながります。
歯磨きに慣れていない犬や年齢を重ねた犬には、「無理のないステップ」と「ポジティブな経験作り」が必要です。最初は慣れさせることに重点を置き、少しずつ歯ブラシや歯みがきペーストに慣らしていきましょう。
また、定期的な獣医師の診察も合わせて行えば、口腔内の状態を専門的に確認しながら、適切なアドバイスやケアの修正を受けることができ、より効果的な予防と早期発見につながります。
人も犬も口腔内の健康は一度悪化すると改善に時間も費用もかかることが多いため、日々のセルフケアと定期的な獣医師の診査を併用して、長く健康な生活を送ることが大切です。
終わりに
犬の歯と口腔衛生を守るためには、正しい知識と継続的なケアが必要です。デンタルケアの基本は、毎日の歯磨きと適切な道具の使用です。特に、犬の部位ごとに注意した丁寧なケアや、嫌がる場合の工夫も重要です。
また、新しい歯ブラシやケア用品を試すことで、より効果的に、そして愛犬にとってストレスの少ない方法を見つけることができます。
(毛先が開いてきたら、否が応でも変えてください。これは人も犬も同じです。)
さらに、定期的な専門家(歯医者ではありません。獣医師さんです。)の診察を受けることで、未然にトラブルを防ぎ、健康な口腔内と全身の健康管理を心がけてください。
犬と飼い主がお互いに笑顔で過ごせるために、日々の歯磨きとケアを続けていきましょう。
最後に…犬の歯磨き指導で困ったら獣医師さんに相談をしましょう!