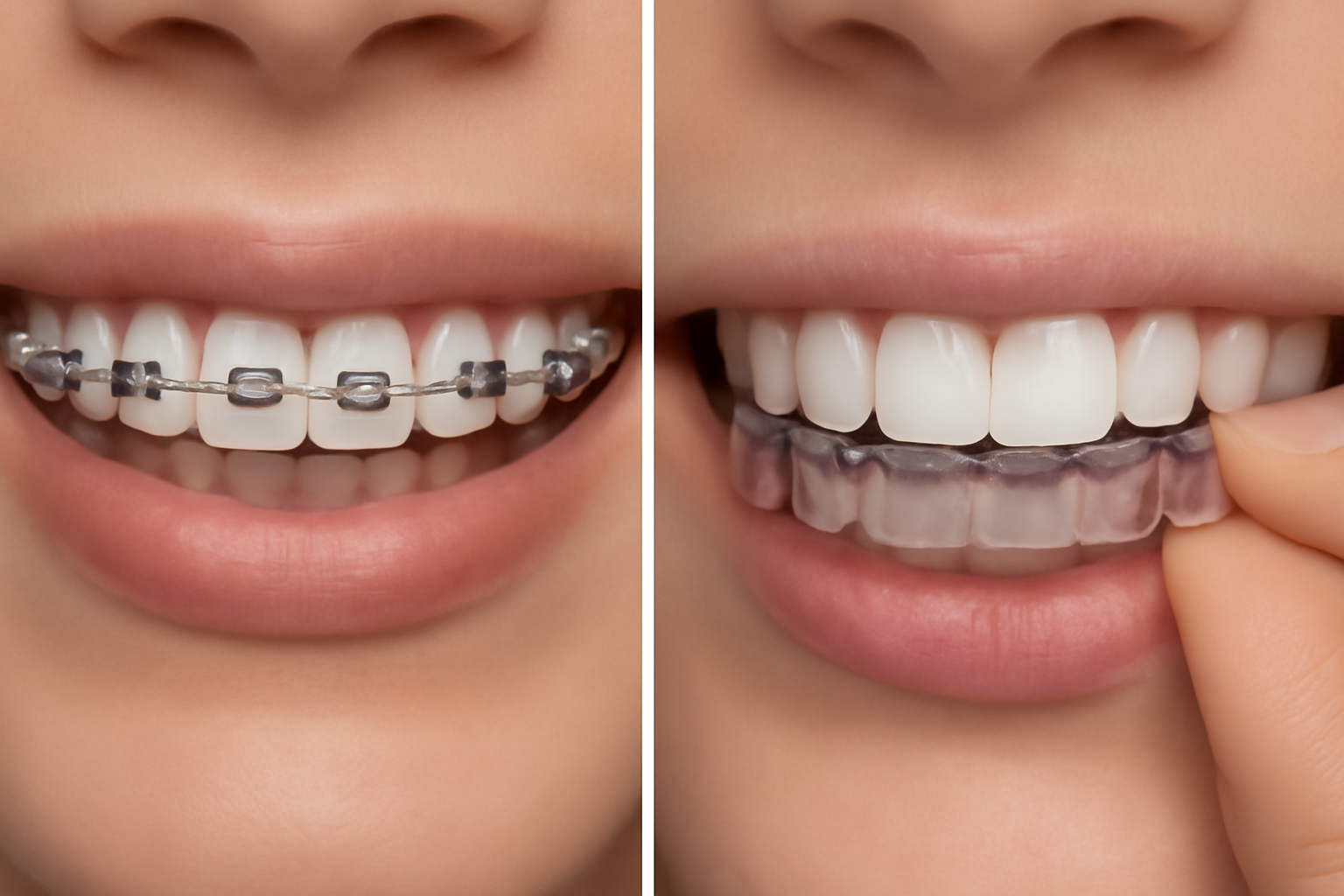2025年11月18日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
現代の子育て環境では、食習慣や飲料の選択に気を配ることが重要となっています。
特に、乳幼児期は、歯の健康にとって非常にデリケートな時期。
歯の発育や歯質の過程がまだ未熟で、歯のエナメル質を溶かす「脱灰」が進行しやすく、放置すれば虫歯や後継永久歯に影響を及ぼす恐れがあります。
活発に行動する子供は、よく清涼飲料水やスポーツドリンクなどを欲しがります。
しかしそれらの摂取が、乳歯のエナメル質の脱灰を促進しやすいことがわかっています。
本コラムでは、これらの飲料が歯に与える影響を紹介し、乳幼児の歯の健康を守るための実践的な予防策について解説します。
1. 飲料のpHと歯への影響
①pHとエナメル質の関係
歯のエナメル質は、人体で最も硬い物質です。
しかしながら、酸性にさらされると、その硬さを維持できずに溶け始めます。
具体的な数値でいうと、pH値が5.5以下になると、エナメル質はより脱灰しやすくなるとされています。
多くの清涼飲料水やスポーツドリンクは、pHが2.8〜4.2と非常に酸性であり、これらを長時間摂取することでエナメル質の脱灰が促進されることが知られています。
特に、炭酸飲料や乳酸菌飲料は、この範囲に含まれ、多くの実験で乳歯の表面に白濁や凹み、脱灰が観察されています。
②実験例
広島大学歯学部小児歯科学講座の山本益枝氏の研究によると、乳歯を炭酸飲料に浸漬させた結果、1日でエナメル質の白濁や柔らかくなる変化が見られ、7日後にはエナメル質の消失や象牙質の露出が確認されました。
同様に、野原智氏ら(松本歯科大学)は、乳児において哺乳瓶による長時間の酸性飲料摂取が虫歯につながるリスクの一因というデータを残しています。
2. 飲料による脱灰と再石灰化のメカニズム
①口腔内のpHバランス
普段の食習慣や飲料の摂取では、唾液の作用により、短時間で口腔内のpHは中性に戻り、脱灰した歯の修復(再石灰化)が行われます。
これは、唾液の緩衝能と呼ばれ、健康な歯ではこれにより虫歯の進行を防いでいます。
②乳幼児の特殊な環境
しかし、乳幼児の場合には、哺乳瓶や長時間の授乳が原因で、「持続的な酸性環境」が長時間続くこともあります。
特に、寝ている間は唾液分泌が減少し、pHが回復しにくくなりやすいのです。
長時間の酸性状態は、エナメル質の脱灰を強め、白濁や初期虫歯のリスクを高めるのです。
③色んな研究での実験結果
乳歯のエナメル質を乳酸菌飲料や炭酸飲料に浸漬させると、6時間経った時点で、明らかなエナメル質の脱灰が認められました。
また浸漬7日目にはエナメル質と象牙質の境界線が曖昧になり、エナメル質が消失して脱灰が進行していることが確認されています。
これらの結果は、長時間にわたる酸性の飲料に触れることが、乳歯の構造を著しく破壊し得ることを示唆しています。
さらに、走査電子顕微鏡(SEM)画像による観察では、脱灰したエナメル質の表面に細かい孔や線維状の構造が現れ、エナメル質の微細な破壊が明瞭に確認されました。
これらの微細構造の変化は、初期の脱灰状態を示しており、適切な予防策を講じる必要性を示しています。
その他の研究では、天然果汁や乳酸菌飲料、炭酸飲料の摂取時間や頻度に伴う脱灰の程度に関するデータも報告されており、長時間の摂取により、エナメルと象牙質の境目や表面が大きく損傷を受けることが示されています。
3. 口腔ケアと予防のポイント
①飲料の選び方と飲み方の工夫
これらの結果を踏まえると、子どもの飲料の選択と与え方に注意が必要です。
⚫︎pH値が高い水やお茶を選ぶ
お水やウーロン茶、緑茶は比較的中性に近いため、歯の脱灰リスクがありません。
⚫︎飲用後には口をゆすぐ
口腔内に滞留した酸や糖分を洗い流すことで、酸の作用を和らげることができます。
⚫︎長時間の飲料摂取や長時間哺乳瓶を用いた与え方は避ける
特に寝かしつけや長時間の授乳は、酸性環境の持続を引き起こしやすく、脱灰を促進します。
⚫︎飲料の頻度をコントロールする
一度に大量の飲料を飲むのではなく、間隔を空けて摂取し、口腔内のpH回復を促しましょう。
ダラダラと飲んでいたら、pHが回復しないため再石灰化できず、歯が溶ける一方になってしまいます。
②乳幼児親のためのアドバイス
⚫︎哺乳瓶の習慣を見直す
長時間口にくわえたままにせず、特に夜間や寝かしつけ前の長時間の摂取を避けましょう。
必要以上の期間、哺乳瓶を使うのではなく幼児期はちゃんと哺乳瓶を使わないようにしましょう。
⚫︎適切な水分補給
水分摂取には、できるだけ中性に近い水やお茶を選びましょう。
⚫︎定期的な歯科検診の推奨
初期の白濁や変色の状態を早期に発見し、適切なケアを行いましょう。
⚫︎歯磨き習慣の早期導入
歯の表面に付着した酸や糖分を除去し、脱灰の進行を防ぎます。
終わりに
飲料水のpH値や摂取時間、頻度が乳歯の脱灰や虫歯リスクに大きく影響することが明らかになっています。
特に乳幼児では、長時間の哺乳や哺乳瓶の長時間利用、夜間の授乳習慣が、酸性飲料やミルクが口腔内に長時間留まる原因となり、エナメル質の脆弱化に繋がります。
乳幼児の歯を健康に保つためには、飲料水の性質と飲み方に十分な注意が必要です。
多くの研究により、低pHの酸性飲料はエナメル質の脱灰を促進し、放置すれば虫歯や歯の損傷の原因となることが明らかになっています。
親御さんや保護者は、子どもへの飲料の与え方や生活習慣を見直し、適切なケアを行うことで、将来にわたる健康な歯を育むことができます。
乳歯の健康は、単に虫歯予防だけでなく、全身の健康や生活の質にも深く関わる重要な要素です。
今後もエビデンスに基づいた情報発信を進め、子どもたちの健やかな成長を支援していきたいと思います。