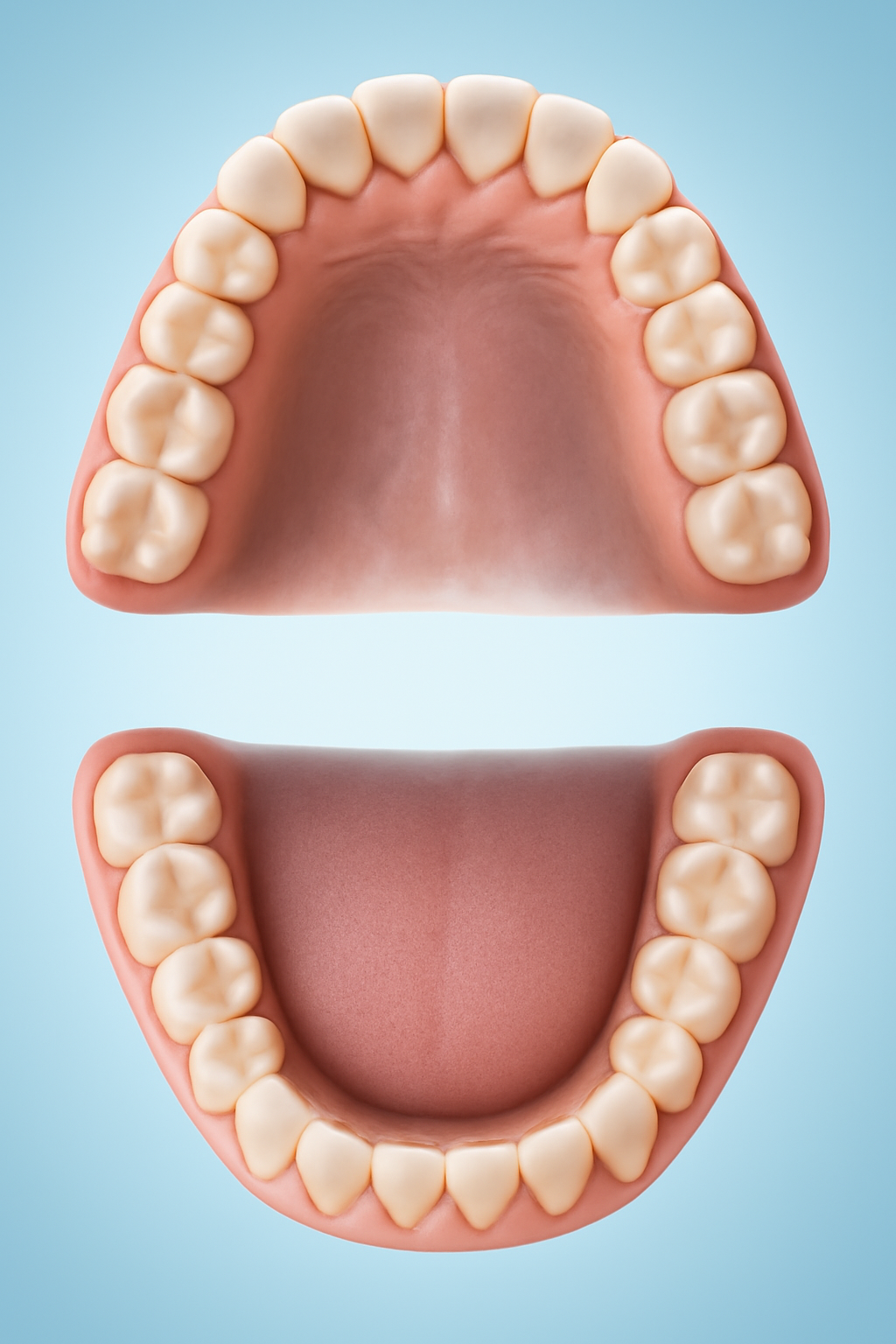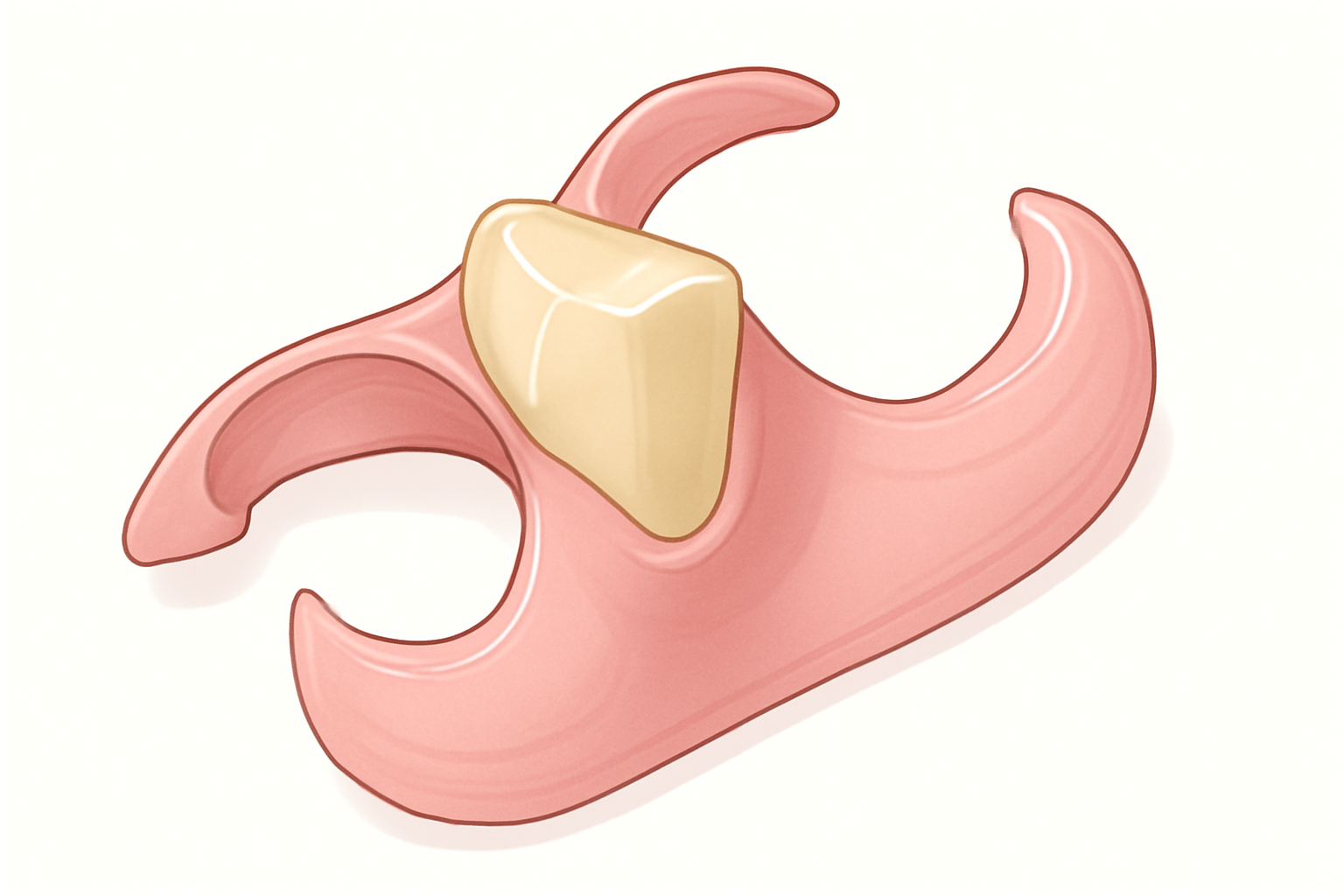2025年6月11日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
口の中に繰り返し現れる小さな潰瘍、痛みがつらくて気になることはありませんか?
それが「再発性アフタ」と呼ばれるもので、何度も繰り返す口内の潰瘍の一つです。
再発性アフタは、非常に一般的な疾患です、国内外の疫学調査によると、成人の約20~60%が一度は経験していると推定されています。また日本人では、30~40代に多く発症しやすい傾向があります。
多くの場合、自然に回復しますが、頻繁に再発する場合や長期間治らない場合は、日常生活の質に大きな影響を及ぼすため、原因の理解と適切な対処が必要です。
今回のコラムでは、その原因や症状、予防法、そして治療について詳しく解説します。病院に行くべき時や、自宅でできるケアについてもお伝えしますので、是非お読みください。
再発性アフタとは何か?
再発性アフタは、口の中の粘膜にできる小さな潰瘍のことで、通常は丸いまたは楕円形で、直径は2~10mm程度です。痛みを伴い、段々と痛みが増すこともあります。
●特徴
繰り返し再発する(数週間から数ヶ月おきに出現)
痛みがひどく、日常生活に支障をきたす場合もあります。
口内のどこにでもできますが、主に頬の内側、唇の内側、舌の側面や裏側、歯茎などに多いです。
再発性アフタの定義と分類
①定義
再発性アフタ(Recurrent Aphthous Stomatitis: RAS)は、粘膜に反復して生じる小さな潰瘍性病変で、通常は無菌性で痛みを伴います。
発症原因は多因子性と考えられており、発症のメカニズムは完全には解明されていません。
②分類
RASは、その症状により以下のように分類されます。
⚫︎小アフタ性潰瘍
直径通常≤10mm、一般的に自己限局性で、治癒後瘢痕を残さない。
再発性アフタ性口内炎の大半がこれで、割合としては85%です。好発部位としては唇の内側、頬の内側、舌、口底、軟口蓋、咽頭などに良く発症します。
1〜2日間の痛みや灼熱感といった前触れが起こったあと、4〜7日間の強い疼痛が発生し、多くは10日以内に自然に治癒します。
ほとんどの場合水疱(水膨れ)は起こりません。
潰瘍の外形は円形または楕円形で、中央部が灰黄色の偽膜で覆われ、その周囲に紅輪があり、わずかに隆起した赤い辺縁を持ちます。
小アフタ性潰瘍は1年に2〜4回再発するといわれていますが、古い潰瘍が治癒する前に新しい潰瘍ができることもあります。
⚫︎大アフタ性潰瘍
直径≥10mm、縁が厚く、治癒に長時間を要し、瘢痕を残すこともあります。
再発性アフタ性口内炎の中で、大アフタ性潰瘍は約10%を占めます。思春期以降に発症しやすく、その症状は小アフタ性潰瘍よりも重篤です。前駆症状として、強い痛みや灼熱感があり、潰瘍は深くて直径が1cmを超えることもあります。
大アフタ性潰瘍は、数週間から数か月続くことが多く、小アフタ性潰瘍よりも治癒までの期間が長いのが特徴です。治療後も瘢痕が残るため日常生活に支障をきたすこともあります。
このタイプの潰瘍は、口唇、軟口蓋、喉の粘膜に多く現れ、発熱、飲み込みにくさ、全身の倦怠感を伴う場合もあります。重症例では、首のリンパ節の腫れが見られることもあり、専門医による治療が必要となることがあります。
⚫︎ヘルペス様アフタ性潰瘍
ヘルペス様アフタ性潰瘍は、再発性アフタ性口内炎の一種であり、その名前の通りヘルペスに似た症状を示しますが、実際にはヘルペスウイルスと関係はありません。このタイプの潰瘍は、全症例の約5%を占め、他のタイプよりも発症年齢がやや遅い傾向があります。
この潰瘍の大きな特徴は、直径1〜3mmの小さな痛みのある潰瘍が多数集まり、紅斑の周囲に発生することです。ただし稀に小さな潰瘍が群発して繋がり、1cm以上に広がることもあります。
潰瘍が現れる前には、痛みや灼熱感といった前兆症状が見られることがありますが、水疱は形成されません。
ヘルペス様アフタ性潰瘍は、約2週間ほど持続し、口内の不快感や痛みが続きます。潰瘍は浅く、中心部は灰黄色をしており、周囲は赤くなっています。治癒の過程では、瘢痕を残すことなく自然に消えるケースが多いのも特徴です。
これらの分類は臨床診断の指標となりますが、確定診断のためには他疾患との鑑別も必要です。
なぜ再発するのか?原因について
再発性アフタの正確な原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関係しています。
①ストレスと精神的負荷
ストレスや精神的な緊張は、免疫の低下を招き、口内の粘膜の抵抗力を弱めます。これにより、口内炎ができやすくなります。
②口腔内の傷や外傷
硬いものを噛んだり、歯磨きの際に歯ブラシで傷ついたりすると、粘膜のバリア機能が低下し、口内炎ができやすくなります。
また、歯並びや不良補綴物が原因となり、何度も同じ場所に咬傷を負うことによっても起こりえます。(ちなみに厳密には歯科要因で起こるアフタは再発性アフタじゃないです。)
③食事の内容
辛いもの、熱いもの、酸性の強い食品(例えば柑橘類やトマト)は、口内粘膜を刺激し、アフタを誘発することがあります。
④栄養不足
特に鉄、ビタミンB12、葉酸の不足は、粘膜の健康を保つのに必要な栄養素が欠乏し、コラーゲンを作り出せずにアフタの発生リスクが高まります。
⑤体調の変化や免疫の低下
風邪や疲れ、不規則な生活、ホルモンバランスの崩れもアフタの再発を促すことがあります。
⑥アレルギーや薬の副作用
特定の成分に対するアレルギーや薬物療法の副作用も、口内炎を引き起こすことがあります。
喫煙習慣やNSAIDs、β遮断薬などによっても起こり得ますが、特に抗癌剤治療中は口内炎が頻発します。
⑦遺伝的要素
家族にアフタが多発する人もいます。そう言った場合は遺伝的に免疫や粘膜の性質が影響している場合もあります。
HLA遺伝子の関与も報告されており、遺伝的素因の重要性が再確認されています。
⑧免疫系統の異常
「免疫システムの異常」も挙げられます。免疫寛容の障害により、口腔粘膜の自己抗原に対して過剰な免疫反応が起こると考えられています。
免疫細胞の一種であるTリンパ球の亢進やサイトカインの異常分泌も関係していると考えられています。
論文では血清中のサイトカインレベルの上昇、特にIL-2、IL-6、TNF-αといった炎症性サイトカインの亢進がアフタの発生と再発に関与していると報告されています。
再発性アフタの症状と経過
⚫︎初期症状
ピリピリした感覚や違和感が起こります。
しばらくして小さな痛みのある潰瘍が現れます。
⚫︎症状が発展
潰瘍が均一の円形または楕円形に拡大します。
痛みが増し、食事や会話の邪魔になってきます。
⚫︎再発頻度
再発頻度は人それぞれで、月1回から数ヶ月に一度とバラツキがあります。何年も再発を繰り返すこともあり、そのため患者さんの生活の質に悪影響を及ぼします
⚫︎回復
1~2週間で自然に治癒します。
しかし再発を繰り返すことが多いのです。
診断と治療のポイント
⚫︎診断は簡単
実物の潰瘍を見て、他の疾患との区別を行います。口内の状態や履歴から再発性アフタと診断されます。
⚫︎治療法
①原因となっている刺激の除去
歯並びや不良補綴物の改善、原因の元となっているアレルギー物質を断つことを行います。
②免疫を高める薬やビタミン剤の処方
栄養不足や薬の副作用などで免疫の低下が起こっている場合は改善します。
血液検査でミネラルやビタミン低値が判明した場合はサプリメントで補います。
③ステロイド軟膏
ステロイド軟膏などを塗布し、治癒を早める場合もあります。
④レーザー治療
患部表面にレーザーを当てることで、治癒を促進します。
予防とセルフケアのコツ
ここでは日々のちょっとした工夫による再発防止を紹介いたします。
①栄養バランスの良い食事を心がける
鉄、ビタミンB群、葉酸を含む食品を積極的に取りましょう。バランスの良い食事が粘膜の健康維持につながります。
②ストレス管理
これが出来れば苦労しませんが、適度な運動や趣味、リラクゼーションを取り入れて、心と体のストレスを軽減しましょう。
③口腔ケア
柔らかめの歯ブラシを使い、傷つきにくい優しいブラッシングを心がけてください。過度な力をかけず、歯磨き粉も刺激の少ないものを選びましょう。
稀にアルコール含有のマウスウォッシュに過敏に刺激がいく場合もあるので、使用していて何度も起こる場合は使用を控えましょう。
④食品・飲料の選択
辛い、熱い、酸っぱい食品は避け、口内を刺激しすぎないように注意しましょう。
⑤定期的な歯科検診
粘膜の状態や口内の健康を維持し、早期発見・早期治療を行うことも重要です。
いつ歯科医に相談すべきか
次の場合は歯科医の診察をおすすめします。
⚫︎潰瘍が何日も治らないとき
⚫︎重度の痛みや出血があるとき
⚫︎頻繁に再発し、生活に支障をきたす場合
⚫︎他の症状(高熱、リンパ節の腫れなど)が出てきた場合
※注意点
稀に口内炎がほかの疾患のサインであることもありますので、自己判断せず、気になる場合は早めに相談しましょう。
再発性アフタの長期的な管理として、粘膜の状態を良好に保つためには、生活習慣の改善や適切な口腔ケアが不可欠です。
また、必要に応じてビタミン補充や薬物療法も取り入れるとよいでしょう。
再発性アフタと鑑別すべき疾患一覧
①ウイルス性口内炎
⚫︎原因
単純ヘルペスウイルス(HSV)
⚫︎特徴
水泡や潰瘍を伴い、ピリピリ感や痛みの前兆あり
⚫︎診断ポイント
前駆症状や水泡形成の特徴から区別
②自己免疫疾患
⚫︎具体例
比較的有名なのはベーチェット病、扁平苔癬、乾癬、全身性エリテマトーデス(SLE)
⚫︎特徴
慢性で潰瘍やびらんが繰り返し発生
全身症状や他の臓器症状を伴うこともある
口腔粘膜以外に皮膚や眼などにも病変
⚫︎診断ポイント
血液検査や臓器症状の有無、及び臨床経過の観察
③腫瘍性疾患
⚫︎具体例
口腔癌、リンパ腫
⚫︎特徴
しこりや持続的な潰瘍、境界不明瞭な潰瘍
痛みが少ない場合もある
進行すると不良肉芽や出血が見られる
⚫︎診断ポイント
組織生検が必要。長期持続や異常所見がある場合は特に疑う
④局所的疾患
⚫︎具体例
口腔外傷、歯肉炎
⚫︎特徴
明らかな外傷や歯科的原因による潰瘍や炎症
⚫︎診断ポイント
局所的な明確な原因の有無、症状の限定範囲
※重要ポイント
⚫︎慢性潰瘍や全身症状を伴う場合
血液検査や画像検査の検討が必要
急性ではなく、長引く潰瘍や痛みには特に注意し、早期診断と適切な治療のために医師に相談することを推奨します。
⚫︎疑いやすい疾患を鑑別するのポイント
①水泡や前駆症状がある場合→ウイルス性口内炎
②繰り返す慢性潰瘍、全身症状を伴う場合→自己免疫疾患(例:ベーチェット病)
③持続的な潰瘍、境界不明瞭、痛みの程度や進行に注意→口腔がん
④頑固な長引く口内炎→血液疾患(例:白血病)の可能性も考慮
このように再発性アフタと鑑別が必要な疾患は、多岐にわたります。
症状の持続期間、痛みの性質、全身症状の有無、臨床所見、および検査結果に基づいて適切に診断し、必要に応じて専門的な検査・治療を受けることが重要です。
終わりに
再発性アフタは多くの人が経験する口内の悩みですが、生活習慣の見直しや口腔ケア、自分にあった適切な治療で予防や症状の軽減が可能です。
痛みを我慢せず、適切なケアを心がけてください。長期的に口内の健康を保つことが、快適な毎日を送るための第一歩です。
もし症状に変化や不安があれば、迷わず歯科医師に相談してください。あなたの笑顔を守るために、私たち歯科も全力でサポートします。