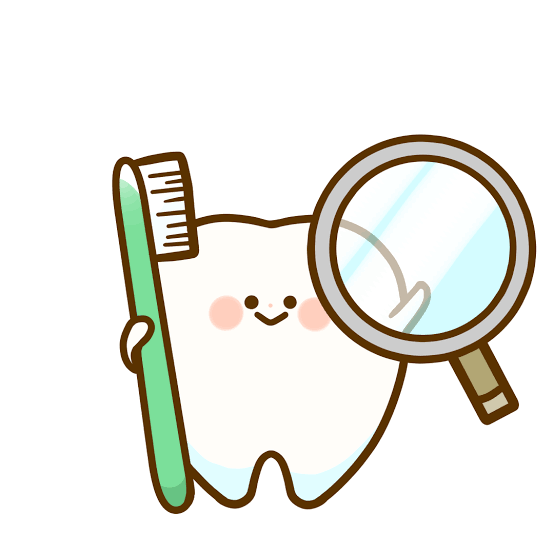2026年2月08日

(院長の徒然コラム)

はじめに
舌は、私たちが食べる、話す、呼吸するなど、生命活動の根幹に関わる重要な器官です。
その舌の動きをサポートするのが、口腔の底と舌の裏側をつなぐ「舌小帯」と呼ばれる薄い膜組織です。この舌小帯が生まれつき短すぎたり、付着位置が前方に寄りすぎていたりする状態を「舌小帯短縮症」と呼びます。
かつてはあまり注目されていなかったり、治療の必要性が疑問視されたりする時期もありましたが、近年ではその機能的な影響が国内外で広く認識され、診断や治療に関する研究が活発に行われています。
本コラムでは、最新の研究データや専門機関の見解を踏まえながら、舌小帯短縮症が子どもの成長に与える影響、診断方法、そして適切な治療の選択肢について、歯科医療の視点から解説していきます。
1. 舌小帯短縮症とは:その解剖と分類
舌小帯は、舌下面の中央に位置し、舌を口腔底に繋ぎ止める薄い組織です。
この小帯が短すぎたり、前方に付着しすぎたりすると、舌の自由な動きが制限されます。
例えば、舌を前に突き出したり、上顎の口蓋に持ち上げたりすることが難しくなります。
短縮の度合いが強いと、舌の先端がハート型にくびれて見えることもあります。
舌小帯短縮症の有病率は、診断基準によって異なりますが、小児期全体で1.7%から10%と報告されています (幅がありますが、どの研究でも10%はいかないです)。
日本では、大学病院の統計で1% 、学生を対象とした調査では2.3%との報告もありますが、近年では4〜10%とする報告も多く見られます。
性差としては男児に多く、女児の1.5倍から3倍の頻度で発生するとされています。
また、遺伝的な要因も指摘されており、舌小帯短縮症患者の約48%に遺伝性が認められたと報告されています。
確かに私の診ていた患者さんでも兄弟や姉妹で舌小帯短縮症の方っていたんですよね。
多くの研究者は舌小帯の分類として、舌の先端、舌下面の中央、舌下ひだ、歯茎といったランドマークを基準に、舌先端型、前方膜型、テント型(中間型)、後方型といった病型に細分化しています。
これにより、舌の可動域制限の程度や重症度をより正確に評価することが可能になっています。
2. 年齢ごとの舌小帯短縮症の影響:多岐にわたる機能障害
舌小帯短縮症は、年齢によって異なる機能障害を引き起こす可能性があります。
①新生児期・乳児期前期:授乳障害と口腔機能の発達
新生児期や乳児期前期においては、主に授乳に関する問題が指摘されます。最新の2026年の論文では、舌小帯短縮症が吸啜困難、早期の疲労、体重増加不良、そして母親の乳頭痛といった問題に関連すると述べています。
別の研究では、対象となった乳児の90.9%が「哺乳不良」を主訴とし、43.1%が「乳頭痛」を、32.1%が「乳腺トラブル」を訴えていました。
しかし、かつての日本では、日本小児科学会が2001年に「本症と哺乳には関連がない、手術を必要とする舌小帯はまれである」との見解を示しており、舌小帯切開はあまり行われなくなっていました。
同様に2024年には東京医科歯科大のホームページで新生児期・乳児期前期の舌小帯短縮症は「哺乳障害とは関係がなく、手術の必要性はない」と述べられていました。
これは、小児科と小児歯科の保健検討委員会が提示した「舌小帯短縮症の考え方」と一致する見解です。
一方で、国際的な見解は異なる場合があります。世界保健機関(WHO)や米国小児科学会 (AAP)は、哺乳障害を伴う舌小帯短縮症に対しては、専門機関への紹介や切開術の検討を推奨しています 。
日本の別の研究者も、システマティックレビューで「哺乳障害を伴う舌小帯短縮症患者に対して、舌小帯切開は有用である」と報告し、積極的に切開手術を行ってきたと述べています。
その研究では、手術を受けた乳児の92.5%で哺乳不良が、80.9%で乳頭痛が改善し、96.8%の母親が治療に「満足」または「非常に満足」と回答しています。
このような意見の相違は、診断基準や評価方法の違いに起因すると考えられます。
新生児の授乳スキル習得は生後1週間以内が重要であり、この時期に介入することが望ましいとされていますが、日本では早期のチェック体制が確立されていない現状があります。
一概に「どちらが正しい」と判断するのは、早計のように思えます。
②幼児期・学童期:構音障害、摂食・咀嚼機能障害、顎顔面の発達
幼児期や学童期においては、構音(発音)や摂食・咀嚼、さらには顎顔面の発達への影響が懸念されます。
就学前の児童や学童において、舌小帯短縮症が /l/, /r/, /t/, /d/, /n/ などの構音障害、複雑な舌運動(突出、挙上、側方運動)の困難、安静時の舌位異常を引き起こすと言われています。
また、慢性的な舌の運動制限は、顎顔面の成長発育に影響を及ぼし、前歯部の開咬や臼歯部の交叉咬合などの不正咬合を誘発する可能性や、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)との関連も示唆されています。
また、幼児期の摂食機能障害(食物をこぼす)も発生しうる可能性があります。
とはいえもちろんそれらは症状の重症度で変わってきます。
2017の日本の研究では、比較的軽度(望月の分類1度)な舌小帯短縮症の患児を対象に、構音評価と咀嚼能率、舌骨上筋群の筋活動量を調査しました。
その結果、軽度な舌小帯短縮症では、構音障害や咀嚼能率、舌骨上筋群の筋活動量への影響が小さいことが示唆されました。
つまり軽度な舌小帯の場合、構音は正常であるか、あるいは言語訓練のみで改善する例が多いということが示唆されています。
摂食・咀嚼機能に関しては、「慢性的な流涎(よだれ)」、「機能不全な嚥下」、「食片をこぼす」ことなどを問題となってきます。
舌は食物を奥歯の間で移動させ、唾液と混ぜ合わせ、食塊を形成して嚥下する上で不可欠な役割を担っています。
舌の動きが制限されると、この協調運動が乱れ、摂食機能障害につながる可能性があります。
「構音障害」についてですが、幼児語(「さかな」を「たかな」など)は舌や口唇の運動が未熟であることによる「機能性構音障害」であり、成長とともに自然に改善することが多いです。
一方で、唇顎口蓋裂や難聴、そして舌小帯短縮症など、原因が明らかなものは「器質性構音障害」として、特別な治療が必要です。
しかし、「わが国では幼児語は舌小帯短縮症、いじめ、欧米への留学などの特別なことがない限り問題にされることはあまりない」という見解も示されており、舌小帯短縮症による機能障害の判断には慎重な姿勢がうかがえます。
特に、日本語は英語に比べて発音が簡単と言われているため、多少の構音障害があっても社会的に受容されやすいという興味深い考察も提示する研究者もいます。
3. 診断と評価:いつ、どのように舌小帯短縮症を見つけるか
舌小帯短縮症の診断は、その機能的影響を正確に捉えることが重要であり、単に形態的な短縮だけでなく、それが生活上の問題を引き起こしているかどうかが判断の鍵となります。
早期発見が重要であるため、小児科医、助産師、歯科医師、言語聴覚士など、様々な専門職の連携が必要です。
①評価ツールと基準
舌小帯の評価には、いくつかの標準化されたツールが用いられます。
⚫︎Hazelbakerの舌小帯機能評価ツール (HATLFF: Hazel Baker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function)
これは授乳期の乳児における舌の形態と機能を評価するために広く用いられています。主に6ヶ月未満の乳児における舌小帯短縮症の重症度を客観的に評価し、手術(舌小帯切除術)の必要性を判定するために開発されたツールなのです。
しかし、日本の研究者の一部は、HATLFFが乳児後期には不向きである点や、「口腔底への付着位置」の判断が不明瞭である点を指摘しています。
⚫︎Marchesanプロトコル
舌の形態と機能の両面から評価を行う混合プロトコルとしてMarchesanプロトコルは作られました。
特に4歳以上の小児においては、このプロトコルを用いて解剖学的・機能的分析を行い、発話への影響を評価することが有用です。
その他研究者独自の評価スコア
例えば伊藤ら (2020) は、Hazelbakerの評価項目を簡素化し、さらに症状(哺乳)の評価を加えた独自の「舌小帯評価スコア」を考案しました。
これは、舌の付着位置や自由度、舌の形態、哺乳の状態を点数化(10点満点中7点以下を手術適応)するもので、舌小帯短縮症の重症度をより客観的に評価する試みです。
これらの評価ツールは、舌小帯短縮症が引き起こす機能障害の有無と程度を客観的に把握し、治療の必要性や適切な介入方法を判断するための重要な手がかりとなります。
②診断時の注意点
例えば東京医科歯科大学「幼児の舌小帯短縮症に遭遇すると直ちに摂食機能障害や構音障害を考え、幼児期前期でも治療の対象であると保護者に伝え、手術を勧める歯科医師がいる」ことへの警鐘を鳴らしています。
舌小帯の異常が見つかったからといって、直ちに治療が必要と判断するのではなく、その機能障害の程度や年齢、子どもの発達段階を考慮した慎重な判断が求められます。
特に、軽度な舌小帯短縮症においては、経過観察や機能訓練で改善する可能性も十分にあります。
4. 治療の選択肢:保存的治療と外科的治療
舌小帯短縮症の治療は、その機能障害の程度、子どもの年齢、そして保護者の意向に基づいて個別化されるべきです。
大きく分けて、保存的治療と外科的治療があります。
①保存的治療:言語療法・口腔筋機能療法
Simkinら(2026) は、舌の可動性が50%未満の短い舌小帯に対しては手術を推奨していますが、良好な可動性がある場合には口腔筋機能療法で十分である可能性を示唆しています。
言語聴覚士による言語療法や口腔筋機能療法は、舌の動きを改善し、発音の明瞭化や摂食機能の向上を目指します。
生後6ヶ月未満の乳児では、吸啜、嚥下、呼吸の評価が優先され、4歳以上の小児では、Marchesanプロトコルなどを用いた詳細な評価に基づき、言語療法が実施されます。
「舌小帯短縮症による機能障害は、特別な場合を除き、3歳以降の機能訓練や構音治療による対応で良く、手術の必要性があるか否かを4~5歳以降に判断しても問題はない」と強調する研究者もおり、保存的治療の重要性を強く示唆しています。
多くの研究で比較的軽度な舌小帯短縮症においては、言語訓練のみで構音が改善した症例が報告されていますので、まずは焦らず経過観察しつつ機能訓練するのが、現在の主流ではあります。
②外科的治療:フレノトミーとフレノプラスティ
外科的治療には、主に「フレノトミー(舌小帯切開術)」と「フレノプラスティ(舌小帯形成術)」があります。
⚫︎フレノトミー(Frenotomy)
舌小帯を単純に切開する手術です。
乳児期の「膜様で半透明、血管の少ない」舌小帯に対しては、迅速で安全なため、診療室で実施可能な選択肢です。
局所麻酔のみで行われることが一般的です。
⚫︎フレノプラスティ(Frenuloplasty)
舌小帯を切開し、組織を再建するために縫合を伴う手術です。
より厚く線維性の舌小帯を持つ年長の小児において、より良い機能的・審美的結果をもたらします。
Z字形成術やダイヤモンド形成術などの術式があり、通常は全身麻酔下で実施されます。
③手術のタイミングと適応
手術のタイミングは個々の臨床的影響に基づいて個別化されるべきです。
⚫︎乳児期
授乳困難が主な問題であり、他の授乳支援策で解決できない場合に手術が適応となります。
最適な介入時期は生後1ヶ月以内とされており、授乳効率の最適化と早期の離乳の抑制を目指します。
⚫︎年長児
構音や顎顔面の発達障害が主な適応となり、術前の言語聴覚評価と適切な外科的計画が不可欠です。
これらの処置は、全身麻酔とより複雑な再建技術を必要とすることが一般的です。
⚫︎CO2レーザーなどの新技術
CO2レーザーやダイオードレーザーといった補助技術が、出血を減らし、手術視野を改善するのに役立つと指摘しています。
ただし、これらの技術は専門的な訓練が必要であり、従来の術式と比較して優れた機能的転帰を示す証拠はまだないとも言えます。
5. 多職種連携の重要性
舌小帯短縮症の診断と治療においては、様々な専門職が連携する「多職種連携」が極めて重要です
小児科医、助産師、保健師などは、新生児期のスクリーニングや、授乳に関する問題の早期発見に重要な役割を果たします。
特に、授乳の専門家からの紹介が、治療へのアクセスにおいて大きな割合を占めているのです。
次に歯科医師、歯科衛生士も口腔内の形態観察や、摂食・咀嚼機能、構音機能の評価を行います。
幼児期以降の舌小帯短縮症においては、適切なタイミングでの介入を判断する上で中心的な役割を担います。
言語聴覚士は構音障害の有無や程度を評価し、言語訓練や口腔筋機能療法を指導します。
手術の適応判断においても、その評価は不可欠です。
このように、各専門職がそれぞれの視点から子どもを評価し、情報を共有することで、舌小帯短縮症による機能障害に対して、より包括的でタイムリーなアプローチが可能となります。
過剰診断や不必要な手術を避け、個々の子どもにとって最適な治療計画を立てるためには、このような連携が不可欠です。
6. 終わりに:舌小帯短縮症への現代的アプローチ
舌小帯短縮症は、かつては軽視されがちだった疾患ですが、近年の研究により、特に乳幼児期の授乳障害、幼児期以降の構音・摂食機能障害、さらには顎顔面の発達に影響を与える可能性が認識され、その重要性が再評価されています。
しかし、その診断基準や治療方針については、専門家間でもまだ意見の相違が見られるのが現状です。
新生児期の授乳障害に対する外科的介入の是非、幼児期の構音障害に対する手術の必要性など、慎重な検討が求められる点が多々あります。
舌小帯短縮症は、子どもの健やかな成長を支える上で見逃せない課題の一つです。
保護者の方々が正しい知識を持ち、専門家と協力しながら、お子さんにとって最適な選択ができるよう、今後も情報提供と研究の推進が求められます。