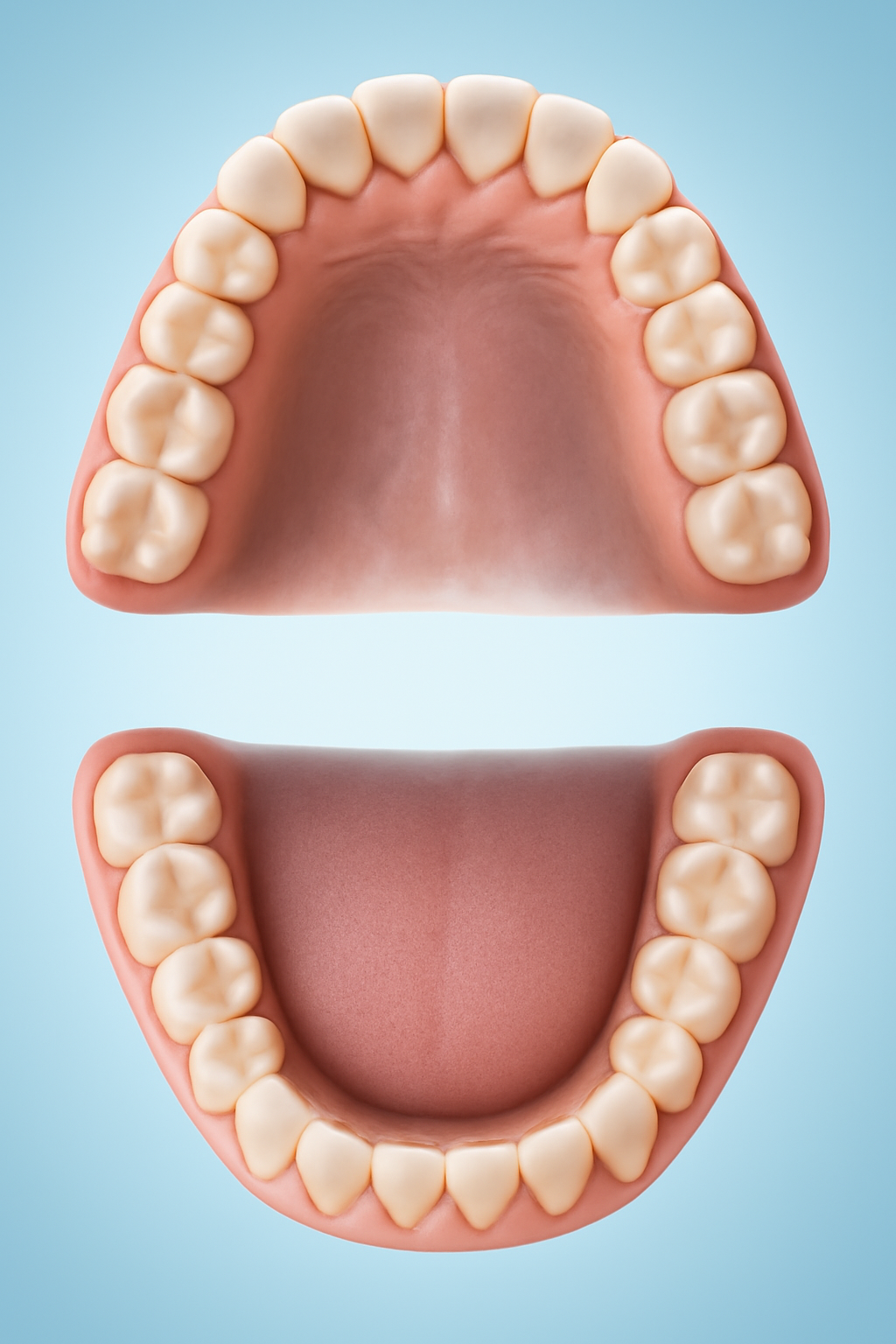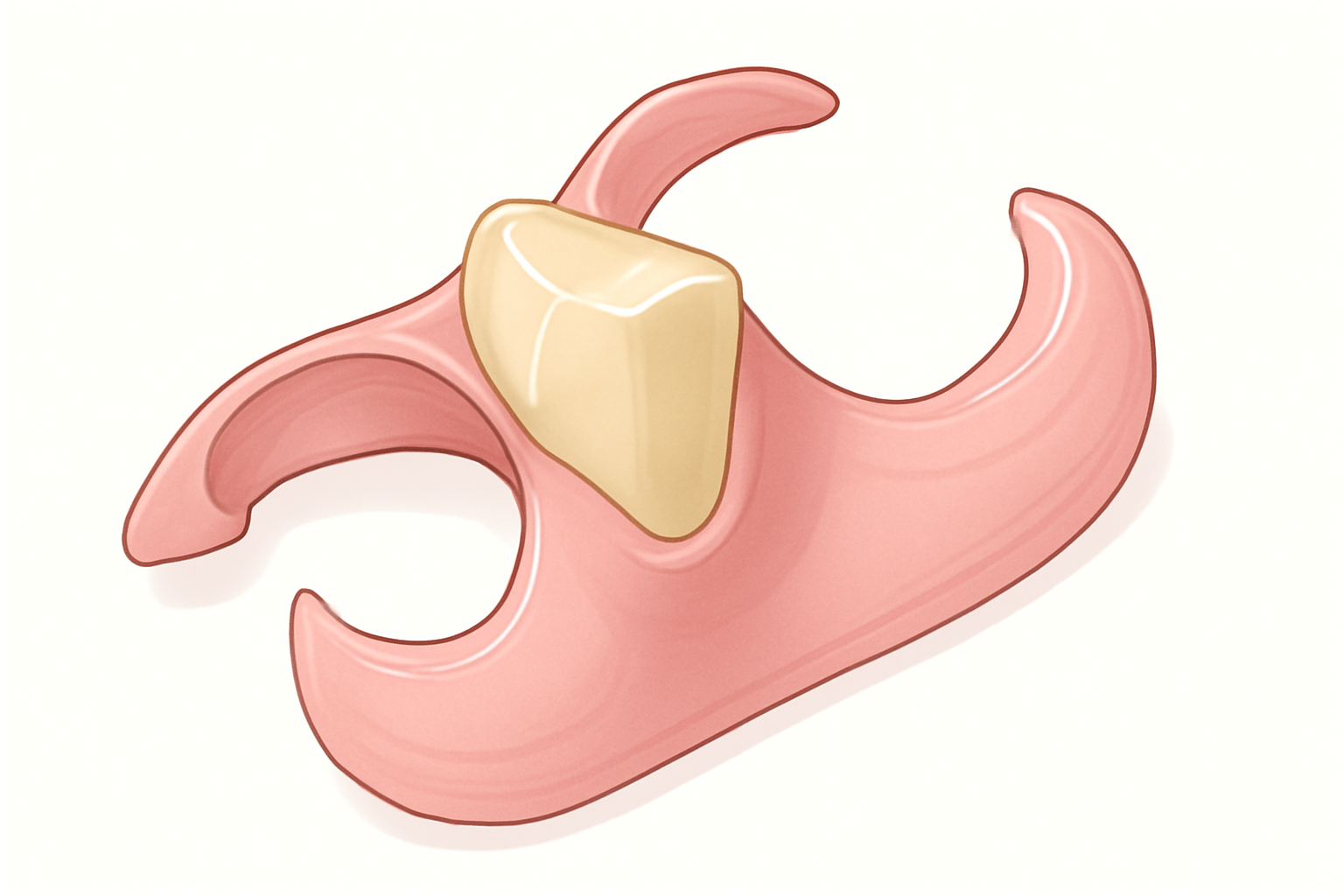2025年10月30日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
こんばんは。今回は極めて専門的…患者さん向けというより歯科医療従事者向けのコラムです。
私は今でこそ外来診療を離れられませんが、以前パーキンソン病や脳卒中、脳性麻痺、筋萎縮性側索硬化症(ALS)といった患者さんの訪問診療をしていた経験があります。
そういった疾患の方を診ている際、ご家族の方より相談されることがあります。
「涎が止まらない。流れ続ける」と。
口腔内の健康管理は歯科医師の重要な役割の一つですが、見過ごされがちな疾患の中に「慢性流涎(まんせいりゅうぜん)」があります。
この疾患は、意図せず唾液が流れ出てしまう状態であり、その原因は神経系の疾患に起因する場合が多いです。
従来、治療にはリハビリテーションや薬物療法、外科的治療などが行われてきましたが、効果や副作用の面で制約もありました。
(特に日本ではリハビリが中心でした。)
しかし、2025年6月に国内で初めて承認された薬剤「ゼオマイン(インコボツリヌストキシンA)」が、新たな選択肢として注目されています。
今回のコラムでは、慢性流涎の背景・診断、従来の治療法、そしてゼオマインの特徴と期待される役割、そして「かかりつけ歯科医師」として何ができるかについて詳述します。
慢性流涎とは何か
①定義と原因
慢性流涎は、唾液の分泌が正常範囲を超え、意図せず口からよだれが流れ出る状態を指します。
通常、人は1日に1~1.5リットルの唾液を分泌し、飲み込みによって無意識に管理しています。
しかし、神経系疾患や筋肉の機能障害などにより、このバランスが崩れると、唾液の排出制御が困難になり、流涎が発生します。
主な原因疾患としては、パーキンソン病や脳卒中、脳性麻痺、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、筋ジストロフィーなどの神経疾患があります。
これらの疾患は、嚥下反射や唾液制御に関わる中枢・末梢神経の障害を引き起こし、流涎を誘発します。
②生活への影響と家族の負担
流涎は見た目や衛生面の問題だけでなく、心理的負担や社会生活の制限ももたらします。
患者は外出を控え、会話や食事が困難となるほか、口周りの炎症や皮膚トラブルも起こりやすくなります。
一方、家族や介護者にとっても、頻繁な衣類の洗濯やケアの負担が増し、精神的なストレスを招きやすい疾患です。
診断のポイントと従来の治療法
①診断のポイント
歯科医師の視点からは、口腔内の観察だけでなく、患者の症状や疾患背景、飲み込みや嚥下の状態を総合的に評価する必要があります。慢性流涎の患者は、口腔乾燥ではなく過剰分泌のために唾液があふれることを理解し、他の疾患との関連を調べることが重要です。
②従来の治療戦略とその課題
従来の流涎治療は主にリハビリテーションや薬物療法、外科的処置を中心に行われてきましたが、それらにはいくつかの重要な課題が存在しています。
まず、リハビリテーションは嚥下や顔面運動の訓練を通じて唾液の制御を改善しようとするものであり、理論的には無害で安全性も高いアプローチです。
しかしながら、実臨床においては効果の個人差が大きく、長期的に持続する効果の証明が限定的であることが報告されています。
また、患者自身や介護者の継続的な努力や根気が必要であり、実施の難しさも反映されています。
そもそもリハビリテーション自体が困難な患者さんが多いのです。
次に、薬物療法の代表格は抗コリン薬であり、唾液腺からの水や電解質の分泌を抑制することで流涎を軽減します。
具体的にはアトロピンなどが使われましたが、(日本ではプロプラノールは慢性流涎の治療薬とは認められていない)副作用の問題が根強く、特に高齢者や神経疾患患者では口腔乾燥、視力障害、心拍数増加、便秘、精神障害など、多岐にわたる副作用が生じるため、長期投与は制限されてきました。
さらに、外科的処置や放射線療法は、唾液腺の一部または全部の摘出を行うものや、唾液腺の働きを遮断する手術を指します。
これらの方法は、効果的に流涎を抑制できる反面、不可逆的な手術リスクや気孔・唾液腺の合併症、感染症、さらには外見の変化や口腔の乾燥といった副作用も伴います。
そのため、患者のQOL維持のためには慎重な選択と長期的なフォローアップが必要とされてきました。
③従来の治療に対する新たなアプローチの必要性
従来の治療法には効果の限界と副作用のリスクが存在し、特に長期的な管理や高齢者のQOL向上には十分とは言えませんでした。
そのため、安全性と持続性を兼ね備えた新たな治療手法の開発は重要な課題となっていました。
そういった流れで近年では、神経調節や薬物送達の精密化、さらには生物学的治療を含む新しいアプローチが模索されていました。
中でも、ボツリヌス毒素の使用が注目されているのは、その高度な局所作用により、全身への副作用を抑えながら効果的な症状改善が期待できる点にあります。
もちろん、従来の薬剤や外科的治療は未だに有効ですが、その効果の限定性や副作用を克服しつつ、安全に長期管理できる治療薬の登場が望まれていました。
そこで白羽の矢が立ったのが先ほどのボツリヌス毒素を利用した薬「ゼオマイン」です(2025年に日本でも承認)
ゼオマイン(インコボツリヌストキシンA)の特徴と臨床における意義
①ゼオマインの概要
ゼオマインは、帝人ファーマが2025年に国内で初めて承認を受けたA型ボツリヌス毒素製剤です。
製品は、ドイツのメルツ社と提携し、日本において共同開発・販売権を有しています。
本剤は、神経系疾患に伴う流涎を対象にした初の薬剤であり、その承認は日本の臨床現場に新風をもたらすものです。
②薬理作用と特徴
ゼオマインは、神経毒素のみを有効成分としたボツリヌス毒素製剤です。
メカニズムは、唾液腺においてコリン作動性神経終末からアセチルコリンの放出を阻害することにあります。
具体的には、唾液腺内に注射された薬剤が、神経終末のシナプス前膜に作用し、アセチルコリンの放出を抑制します。
これにより、唾液の水分と電解質の分泌が低下し、過剰な唾液分泌を効果的に抑えることができます。
※歯科学生の方へ
唾液線は交感神経と副交感神経の両方で支配されていると習いましたよね?
アセチルコリンは副交感神経からの神経伝達物質です。そしてリラックスしている時に優位となるのは副交感神経…
つまり慢性流涎の時の原因となる副交感神経から放出されるアセチルコリンを阻害すれば、流涎は止まるというメカニズムですね。
このメカニズム顎関節症の治療目的に行われる「ボトックス注射」とも一緒です。
③使用方法と投与スケジュール
ゼオマインは、両側の耳下腺および顎下腺に計100単位を分割して注射します。
具体的には、左右の耳下腺に各30単位、顎下腺に各20単位を注射します。
この投与は、患者の状態に応じて減量や再投与も可能であり、再投与間隔は原則16週以上と定められています。
(ただし、臨床現場では14週間まで短縮されるケースもあります。)
④臨床効果と副作用
本剤の臨床試験結果によると、注射後約4ヵ月間、流涎の症状が改善されることが確認されており、効果の持続性は高いと考えられます。
また、国内外の疫学調査や臨床試験では、多くの患者において良好な効果と安全性が示されています。
副作用については、注射部位の腫れや痛み、一時的な嚥下障害が報告されましたが、全体としては耐容性が良好であり、重篤な副作用は稀です。
このため、従来の薬物療法と比較して、安全性の面で大きなアドバンテージがあると考えられます。
⑤社会的・医療的な意義
ゼオマインの承認は、従来の治療法に加えて、局所的かつ可逆的な作用を持つ安全な薬剤の選択肢を提供します。
特に、外科手術や放射線療法に抵抗感やリスクを感じる患者にとって、局所注射による効果的な症状緩和は非常に魅力的です。
さらに、慢性流涎は高齢化社会における高齢者のQOLを著しく低下させる疾患であり、その管理には多職種連携が求められます。
我々歯科医師は、唾液制御の第一線に立つ存在として、ゼオマインの適応を見極め、患者のQOL改善に寄与できる点で、重要な役割を担う義務があります。
今後の課題
①臨床現場への普及と期待
ゼオマインの国内承認により、高齢化社会において増加する神経疾患患者のQOL改善に大きく寄与すると期待されます。
特に、従来の薬物療法の副作用や外科的治療のリスクを回避しつつ、安全に長期管理できるという点は、医療従事者や患者、家族にとって魅力的です。
歯科医師はもちろん、神経内科や耳鼻咽喉科など多職種が連携して適切な患者選定を行い、治療計画に組み入れることが重要となります。
今後、臨床ガイドラインの整備や使用の標準化、投与後の経過観察といった運用面の検討も進められるでしょう。
ただし、一般的なかかりつけ歯科医で薬を準備できる時代は「まだ」来ていないと言えます。
まずは「慢性流涎」について歯科医師が正しい知識を持ち、患者さんを中核病院に紹介できる準備をしましょう。
医療従事者の「知らなかった」は許されないのですから。
②研究とエビデンスの蓄積
ゼオマインは、日本だけでなく海外でも広く承認されており、臨床データも豊富に蓄積されています。
ただし、日本人特有の臨床反応や副作用の発生頻度、最適投与量の検討など、各国の医療状況や患者背景に応じた適応拡大や使用法の最適化が求められます。
また、長期投与による効果持続性や安全性、他疾患併存患者への適応、費用対効果の分析など、多角的なエビデンス蓄積が必要です。
今後薬剤の局所注射法や投与スケジュールの最適化、必要に応じた再投与のタイミングなども検討課題です。
③課題と注意点
ゼオマインはまだ日本では新参者です。先ほどの課題も含めてピックアップしていきます。
⚫︎適応拡大の慎重な評価
重篤な神経疾患や顔面神経麻痺などの特殊例に対しての有効性や安全性のデータ収集が必要です。
⚫︎適正使用と教育
医師や歯科医師への適切な投与法に関する知識普及と、患者への説明の徹底が求められます。
そもそも「慢性流涎」に対する知識が、日本の歯科医師は劣っていると言えます。
⚫︎費用問題
新薬の高額性や保険適用範囲の拡大も将来的な課題となるため、経済的合理性も議論される必要があります。
④医療連携における役割と期待
高齢者や神経疾患患者の日常生活の向上には、歯科医師だけでなく、医師、看護師、リハビリスタッフ、介護者など様々な職種が重要な役割を担います。
ゼオマインという薬剤への知識や「慢性流涎」に対する知識をしっかり医療従事者全体が身につけることで、地域医療や在宅医療においても各々が円滑に役割を果たすことができるでしょう。
また、患者や家族の理解と協力を促すための啓発活動や教育も不可欠です。
疾患の早期発見と適切な治療開始により、疾患の進行を抑え、より良いQOLを実現することが今後の目標です。
おわりに
慢性流涎は、多くの神経疾患患者にとって、日常生活の質を著しく低下させる重要な症状の一つです。
従来の治療法には効果の限定や副作用のリスクが伴い、患者やその家族にとって大きな負担となっていました。
しかし、2025年に承認されたゼオマインは、局所的かつ持続的な改善をもたらす新しい治療選択肢として、医療の現場に革新をもたらす可能性があります。
今後は、医療従事者間の連携体制の構築やエビデンスの蓄積を通じて、より安全で効果的な治療法の普及を目指す必要があります。
特に、歯科医師はこの新たな選択肢を理解し、患者の状態に適した適切な診断と治療を提供する役割を担っています。
本コラムが、歯科医師や医療従事者の皆様にとって、慢性流涎の理解と新たな治療選択肢の一助となれば幸いです。