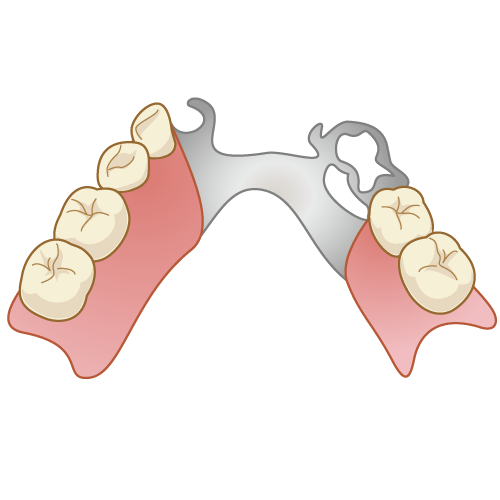2024年12月02日

(院長の徒然ブログ)

アナフィラキシーショックとは?
歯科偶発症シリーズも第5回目になってきました。今回は死亡する症例もあるアナフィラキシーショックです。
アナフィラキシーショックとは、薬物などのアレルギー反応のうちIgE抗体を介したI型アレルギーによってショック状態になることです。
発症機序に IgE抗体が関与しない場合アナフィラキシー様反応と呼ばれるものもありますが、対応としてはほぼ同一なので、ここでは割愛致します。
発生率は低く、滅多に起こることはないのですが、発症すれば症状は深刻で進行が早く、判断が遅れれば命に関わります。
歯科で最も警戒しなければいけない偶発症の一つです。
歯科でのアナフィラキシーショックの原因
もちろんありとあらゆる物にアレルギーというものは起こり得るのですが、歯科分野で良く原因として挙げられるのが、抗生物質,鎮痛剤,ヨード製剤などです。
歯科用局所麻酔薬自体のアナフィラキシーは滅多にありません。しかし添加されている防腐剤や安定剤にアレルギー反応が起こる方もいらっしゃいます。
局所麻酔薬のうちスキャンドネスト®には添加物は含まれていないので、事前に局所麻酔薬の含有製品にアレルギーがある方は申告されてください。
その他,デンタルコーン、歯周炎治療用ペースト、根充剤、消毒剤(グルコン酸クロルへキシジンなど)、現在はあまり使われませんがホルムアルデヒドを含有する根管治療薬(ホルマリンクレゾール®や、ペリオドン®)によるアナフィラキシーショックが報告されています。
注意が必要なのは、治療後に突然起こるアナフィラキシーショックです。
根の治療に使う根管治療薬は、体には直接触れない部分に入れるため、もしアレルゲンとなってもすぐには反応しません。
この根幹治療剤によるアナフィラキシーショックは10例以上の報告がありますが、通常のアナフィラキシーショックとは異なり、歯科治療後数時間から10時間に遅れて発症する傾向があるのです。
時に遅延するのがパラホルムアルデヒドで、歯の中という直接体に触れない構造物の中に入れられている点と、パラホルムアルデヒドが徐々に気化してホルムアルデヒドとして遊離する点により、遅れてしまうと考えられています。
またアレルゲンは薬品関係だけとは限りません。
某漫画で有名になりましたが、医療関係で使用する手袋やラバーダム防湿に使うラバーダムのラテックスゴムに対してアナフィラキシーショックが発症する可能性もあります。
これを特にラテックスアレルギーと言います。
アナフィラキシーショックの症状
一般的にアナフィラキシーショックは、起物質アレルゲンに暴露してからすぐ、数分以内に生じます。皮膚接触や経口投与ではやや遅く30分以内に出てきます(ラテックスアレルギーもこれ)。
症状は多彩で、皮膚や粘膜面、消化器官、呼吸器、循環器症状が現れます。
発症した時に症状の出現順序を把握しておくのは重要で、まず気分不良、唇や手足のしびれ感、悪心、眩暈,耳鳴、胸部不快感,便意、尿意などを自覚します。
そして次いで咳、くしゃみ、皮膚の痒み,皮膚の表面の紅潮,蕁麻疹,血管性浮腫などが生じます。
特にわかりやすいのがこの皮膚症状なので、絶対に見過ごさないのが重要なのです。
その後更に顔面蒼白になり喘鳴や呼吸困難,下痢や失禁、血圧低下、頻脈,不整脈を生じていきます。
流石にこの時にはエピペンなどによるアドレナリン投与などの救急対応や、救急車を呼んだりしていると思いますが、この後も放置するとやがて意識消失,呼吸停止,心停止となり死亡します。
アナフィラキシーショックの対応
アナフィラキシーショックは歯科偶発症で最も処置には迅速さが要求される症状の一つです。
まずは医療用モニターを装着して速やかにバイタルサインのチェックを行い、水平位で両下肢を挙上して少しでも血圧低下を抑えましょう。
次いで酸素投与を行っていきましょう。
アウトドアに詳しい人ならご存知(スズメバチ対策)かもしれませんが、アナフィラキシーの第一選択薬はエピネフリン(アドレナリン)です。
というのも、死亡に至る1番の原因は極端な血圧低下に依る面が強いので、血圧を上げてあげることが寛容なのです。
アナフィラキシーショックが起こったら、まずさっさと119番通報を済ませて、エピネフリンを0.2~0.5mg皮下注射もしくは筋肉注射します。
症状が軽かろうがなんだろうが、絶対に救急車は呼んでください。
エピネフリン投与後も症状が続くようなら、エピネフリン投与を15分ごとに繰り返して、昇圧を維持してあげます。
もし静脈路を確保できる設備があるなら静脈注射も行います。
最近ではエピペンという簡易的に使えるエピネフリンもあるので、速やかに対応を行えるようになっています。
先ほどの続きで、静脈路が確保できるならば更にステロイド、抗ヒスタミン薬を静脈注射して、アレルギー反応自体を沈静化させましょう。
気管支喘息症状がみられればアミノフィリン(ネオフィリン®) を投与します。
アナフィラキシーショックで注意すべき点として、呼吸困難の場合気道の確保が難しい場合があります。
アナフィラキシーショックショックの場合、喉頭浮腫により気道狭窄している可能性があるため、良く救急救命対応で示されるような下顎挙上などの用手的な気道確保法が有効とならない場合があるからであるのです。
アレルギー反応により喉頭浮腫が進行し、咽喉頭腔が物理的に狭まり気道狭窄が生じた場合,気管内挿管や気管切開などによらないと気道が開通しない可能性があります。
そういった観点からも、1歯科医院で対応しようなどとは考えず、救急車は必ず呼んでください。
アナフィラキシーショックの予防の難しさ
アナフィラキシーショックの予防の難しさはその特性にあります。
皆さんは「スズメバチに2回目刺されたら死亡した」という話を聞いたことはありますか?
原則的にいくらその人のアレルゲンとなり得る薬物だからといって、最初の投与ではアナフィラキシーショックは起こらないのです。
もちろん医療従事者は予防策としては、「詳細な問診」を行い、患者本人だけでなく家族のアトピー性要因があるかどうかの確認が大切です。
しかし問診上、一度投与して安全だったこともある薬物でも、今現在安全であるとは言い切れないのです。
また、一度も投与されていない薬が安全とも限りません。
知らないうちにその薬物の成分が体内に侵入したことがあるかもしれないし、別の薬物(例えば市販のお薬)にそのアレルゲンとなる物質が含まれていた可能性もあります。
そもそも投与されてなんの異常も症状も出なかった時、患者さんは薬物の詳細を覚えていないケースが殆どです。
また、アレルゲンとなる物質と違う物質でも、化学構造が類似した物質に対してアナフィラキシーショックが生じることがあります。
少なくとも、アレルゲンの特定ということに関しては、問診だけで対応できるものでは無いと考えます。
診療中にアレルギー発症の可能性があると考えられた場合は、薬物使用は慎重に検討して、危険回避のために高次医療機関に検査を依頼するという「安全第一」な選択をすることが重要です。
終わりに
いかがでしたか?
アナフィラキシーショックは、特に事前にリスクをチェックしておくことももちろん大事ですが、起こった時の万が一の備えを万全にしておくことも大事です。
発症した際には、医院で可能な限り応急処置しつつ、連携医院に速やかに患者さんを診てもらえるように、医療連携をしっかりして参ります。