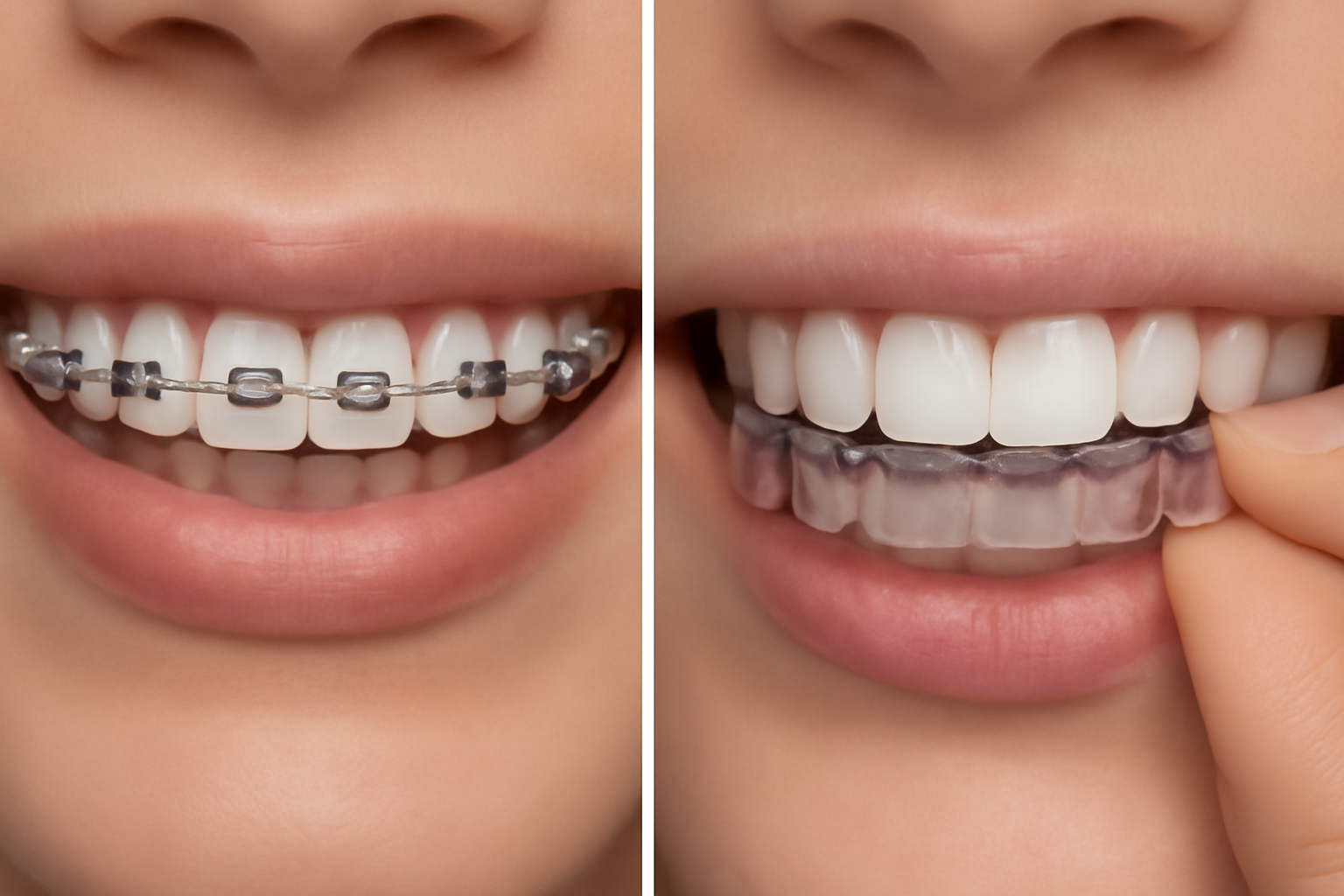2025年4月10日
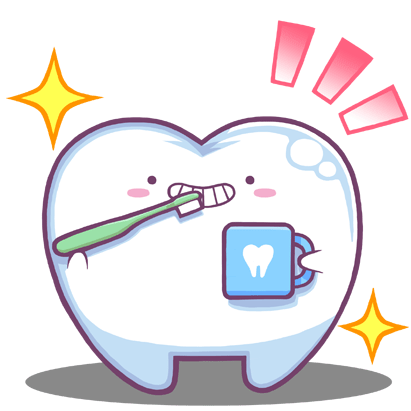
(院長の徒然ブログ)

はじめに
虫歯は、歯質が酸によって侵食されることによって発生する病気です。
最近は意識が上がり、定期検診を受けてくださる方も増えましたが、まだ多くの方が「痛くない歯はそのままにしておいても大丈夫」と考えがちです。
しかし果たして本当にそうなのでしょうか?
本コラムでは、痛くない虫歯のリスク、治療の重要性、そして予防策について詳しく解説します。
虫歯の進行と痛みの関係
虫歯は、初期段階では痛みを伴わないことが多いです。この段階では、エナメル質が侵食されているものの、神経に刺激が伝わる象牙質の部分まで虫歯が達していないため、痛みを感じることはありません。
しかし、痛みがないからといって、虫歯が進行していないわけではありません。
虫歯の段階
①初期齲蝕(C0)
初期段階では、歯の表面に白い斑点が見られることがあります。この段階では、まだ痛みは感じませんが、放置すると虫歯は進行し、エナメル質がさらに侵食されていきます。
②エナメル質齲蝕(C1)
エナメル質への虫歯の侵食が更に進んだ段階です。歯の表面に明らかな穴や引っかかり、凹みが見られます。(実質欠損)
しかしこの段階でも、まだ痛みは感じません。更に放置すると虫歯は進行し、エナメル質を突破して象牙質に侵食されていきます。
この段階では自覚症状もほぼ無いため、この虫歯治療目的で来院される方は稀です。
③象牙質齲蝕(C2)
虫歯が進行すると、象牙質に達し痛みを感じることがあります。
この段階では、冷たいものや甘いものに対して敏感になることがあります。
それでもまだ虫歯は神経の部屋には達しておらず、詰め物などで治るケースが多いです。この段階では痛みによる自覚症状があり、歯医者に退院する方が多いです。
虫歯の部分も黒くなってわかるケースが多いのですが、急速に進行した虫歯は黒くないケースもあり、奥歯だと直接見ることもできないので、この段階でも来院されない方もいらっしゃいます。
④象牙質齲蝕(C3)
虫歯が神経に達すると、冷たい物やあったかい物がしみるだけでなく、何もしなくても痛く、夜寝れないくらいの激しい痛みを伴うことが多く、治療が必要になります。
この段階では、根管治療が必要になることもあります。虫歯で神経が死んでしまい、骨にまで達している場合では抜歯が必要なケースもあります。
流石に大きく歯が欠けてくるのと痛みが強いので、ほとんどの患者さんは気づいて歯医者に来院されます。
④象牙質齲蝕(C4)
虫歯がさらに侵食し、歯の頭の部分(歯冠部)を完全に崩壊させてしまい、根の部分だけ残った状態です。C3と同様に激しい痛みを感じるケースもあれば、逆に神経が虫歯に食べ尽くされて死んでしまって痛みを感じないケースもあります。
また、ばい菌の産生物や穴に食物残渣は溜まり、口臭に影響することもあります。
こうなる前にC3を通るため、痛みが引いたら治ったと勘違いしないようにしてください。さらに放置するとばい菌が骨にまで達し、抜歯になるケースがあります。
痛くない虫歯を放置するリスク
痛くない虫歯を放置することには、いくつかのリスクがあります。
進行の可能性
痛みがないからといって、虫歯が進行しないわけではありません。初期虫歯が放置されると、徐々に進行し、最終的には神経に達することがあります。
治療の長期化・複雑化
虫歯が進行することで、治療が複雑になり、費用や治療時間が増加する可能性があります。
初期段階での治療は比較的簡単で、樹脂を埋めたりする治療(コンポジットレジン修復)だけで済み費用も抑えられますが、進行した虫歯は根管治療や抜歯が必要になることがあります。
根管治療は何度か根の中の管を消毒せねばなりませんし、抜歯した場合はその後の補綴もあるので回数や時間が嵩みます。
全身への影響
以前もコラムで話しましたが、虫歯は口腔内の健康だけでなく、全身の健康にも影響を与えることがあります。
虫歯が進行すると、感染症のリスクが高まり、全身に影響を及ぼす可能性があります。
歴史上の人物には虫歯で亡くなった方もいらっしゃいます。
痛くない虫歯も治療することの重要性
痛くない虫歯でも、治療が必要な理由は以下の通りです。
早期発見・早期治療
定期的な歯科検診を受けることで、初期虫歯を早期に発見し、治療することができます。これにより、虫歯の進行を防ぎ、健康な歯を維持することができます。
さらには治療費や治療期間の削減にもつながり、結果的に色んな意味で患者さんの負担を減らせます。
予防的治療
初期虫歯の場合、フッ素塗布やシーラントなどの予防的治療が効果的です。これにより、虫歯の進行を防ぐことができます。
定期検診を受けていると行えますし、1年に一回はレントゲンを撮って検査することをお勧めします。
口腔内の健康維持
虫歯を放置すると、口腔内のバランスが崩れ、他の歯や歯周組織にも悪影響を及ぼす可能性があります。
噛み合わせが崩れれば他の歯の当たりが強くなり、歯周病やひどい場合は動揺してきます。
歯と歯の間で片一方が虫歯になると、そこに残渣が溜まりもう一方も虫歯になりやすくなります。
健康な口腔環境を維持するためには、虫歯の治療が不可欠です。
抜歯を防げるかもしれない
前述の通り、痛みがない虫歯は初期齲蝕だけでなく、進行して神経が死んでしまった歯も痛みがないのです。
そういった歯は少しでも早く治療に取り掛かった方が、歯を残せる可能性が上がります。
(もちろんそこまで放置して欲しくはないですが)
虫歯の治療法
虫歯の治療方法は、虫歯の進行度によって異なります。
(C0)フッ素塗布
初期虫歯の場合、フッ素を塗布することでエナメル質を再石灰化させ、虫歯の進行を防ぐことができます。
フッ素は、歯の表面に取り込まれ、酸に対する抵抗力を高めます。MIペーストを使用するのもお勧めです。
(C0)シーラント
特に奥歯の溝に虫歯ができやすい場合、シーラントを施すことで虫歯のリスクを低減できます。シーラントは、歯の溝に樹脂を塗布し、食べ物や細菌が入り込むのを防ぎます。
(C1、C2)充填治療
実質欠損があり、神経まで達してない虫歯の場合、虫歯部分を削り、樹脂の充填材で埋める治療(コンポジットレジン修復)が行われます。これにより、虫歯の進行を防ぎ、歯の機能を回復させます。
(C1、C2)補綴治療
実質欠損があり、神経まで達してない虫歯の場合だけど虫歯の範囲が大きいときは、虫歯部分を削り、型を取って詰め物を装着していく治療が行われます。
これもまた、虫歯の進行を防ぎ、歯の機能を回復させます。最近の保険治療では白い詰め物被せ物もできるようになっています。(一部条件あり)
C3、C4の根管治療が終了した後も補綴治療を行うケースがほとんどです。
(C3、C4)根管治療
重度虫歯の場合、神経が感染している可能性があるため、根管治療が必要です。
化学的機械的に根の管の中の汚れや細菌をとっていきます。
この治療では、感染した神経を取り除き、根管を清掃・消毒した後、最終的な根の薬を充填します。その後補綴治療へ移行します。
(C3、C4)抜歯
虫歯が非常に進行している場合、歯を抜くことが必要になることもあります。抜歯後は、インプラントやブリッジ、義歯などの補綴治療が考慮されます。
虫歯の予防策
結局のところ虫歯はいかに予防するかにかかってきます。虫歯を防ぐためには、以下の予防策が有効です。
①定期的な歯科検診
患者さんに合った期間ごとに歯科検診を受けることで、虫歯の早期発見が可能です。(平均は3ヶ月ですがお口の中のリスクによります)
定期的なクリーニングも、虫歯予防に役立ちます。
適切な口腔衛生
毎日の歯磨きとフロスの使用は、虫歯予防に欠かせません。特に、就寝前の歯磨きは重要です。
可能であれば毎食後、必ずフッ化物を利用して清掃してください。(フッ素を利用しない歯磨きは虫歯予防効果がほとんどないという研究結果もあります。)
うがいは2回まででお願いします。
また歯ブラシによる歯磨きだけでは虫歯の予防効果はあまり望めません。
歯垢除去率はフロスなどの補助器具を使ってこそなので、必ず使用してください。
食生活の見直し
甘いものや酸性の飲食物を頻回または習慣的に摂取されている方は、とても虫歯のリスクが高いと言えます。
清涼飲料水やアイスクリームなど、頻繁に甘いものを飲む習慣がある方は見直してみてください。
またそういった飲食物を摂取した場合は、きちんと直後にブラッシングをしましょう。
時間がない場合でも、マウスウォッシュなどでうがいし、中和を心掛けてみてください。
フッ素の活用
前述の通りフッ素入りの歯磨き粉やフッ素塗布を利用することで、エナメル質を強化し、虫歯のリスクを低減できます。
ただし、大人になるとフッ素の取り込み率は極端に下がってしまいます。
MIペーストなどの再石灰化を促すペーストを使用するのも良いでしょう。
食事と食事の期間を空ける
歯が虫歯にならないために再石灰化とは重要なプロセスですが、食事を終えて歯の清掃をきっちり終えたのちに、唾液から再石灰化成分が供給され開始されます。
食事と食事の間が短いと、その再石灰化をしてくれる期間が充分確保できません。
食後に歯をきれいにした後は、充分再石灰化する猶予を与えましょう。
歯の再石灰化のメカニズム
歯の再石灰化は、虫歯の初期段階である脱灰(エナメル質のカルシウムとリンが失われるプロセス)を逆転させる重要な過程です。
この過程は、歯の健康を維持し、虫歯の進行を防ぐために不可欠です。
①脱灰と再石灰化のバランス
歯のエナメル質は、主にハイドロキシアパタイト(Ca10(PO4)6(OH)2)という物質から構成されています。口腔内のpHが低下すると、酸性環境が形成され、エナメル質のカルシウムとリンが溶出し、脱灰が進行します。
この脱灰が進むと、歯の表面が弱くなり、虫歯が発生するリスクが高まります。
再石灰化は、脱灰によって失われたミネラル(主にカルシウムとリン)が再びエナメル質に取り込んでいきます。
再石灰化は、口腔内のpHが中性またはアルカリ性に戻ることで促進されます。
再石灰化のメカニズム
再石灰化は、以下の要因によって促進されます。
①唾液の役割
唾液は、再石灰化において重要な役割を果たします。唾液には以下の成分が含まれています。
カルシウムとリン
唾液中にはカルシウムイオン(Ca²⁺)とリン酸イオン(PO₄³⁻)が含まれており、これらがエナメル質に再び取り込まれることで再石灰化が進行します。
緩衝作用
唾液は酸を中和する緩衝作用を持ち、口腔内のpHを中性に保つことで、脱灰を防ぎ、再石灰化を促進します。
抗菌作用
唾液中の抗菌成分(リゾチームやラクトフェリンなど)は、口腔内の細菌の活動を抑制し、虫歯のリスクを低減します。
フッ素の効果
フッ素は、再石灰化を促進する重要な成分です。フッ素は以下のように作用します。
①フルオロアパタイトの形成
フッ素は、ハイドロキシアパタイトと反応してフルオロアパタイト(Ca10(PO4)6F2)を形成します。フルオロアパタイトは、ハイドロキシアパタイトよりも酸に対する耐性が高く、虫歯のリスクを低減します。
②ミネラルの取り込み促進
フッ素は、エナメル質の表面に存在するカルシウムとリンの取り込みを促進し、再石灰化を助けます。
食事と栄養素の重要性
食事も再石灰化に影響を与えます。
カルシウム
乳製品や緑黄色野菜に含まれるカルシウムは、再石灰化に必要なミネラルを供給します。
リン: 魚や肉、卵などに含まれるリンも、再石灰化に寄与します。
ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を維持するために重要です。
終わりに
痛くない虫歯は、見えないところで静かに進行している可能性があります。
痛みがないからといって放置することは、将来的な問題を引き起こすリスクがあります。定期的な歯科検診を受け、早期発見・早期治療を心がけることが、健康な口腔環境を維持するために重要です。
また、重度の虫歯の痛みが消えたからといって治ったわけではなく、より深刻なステージに移行したに過ぎません。
手遅れになる前に必ず歯科医院を受診するようにしてください。
虫歯に関する疑問や不安がある場合は、躊躇せずに当院にご相談ください。健康な歯を保つためには、日々のケアと定期的なチェックが欠かせませんので、しっかり歯を守るお手伝いをさせてください。