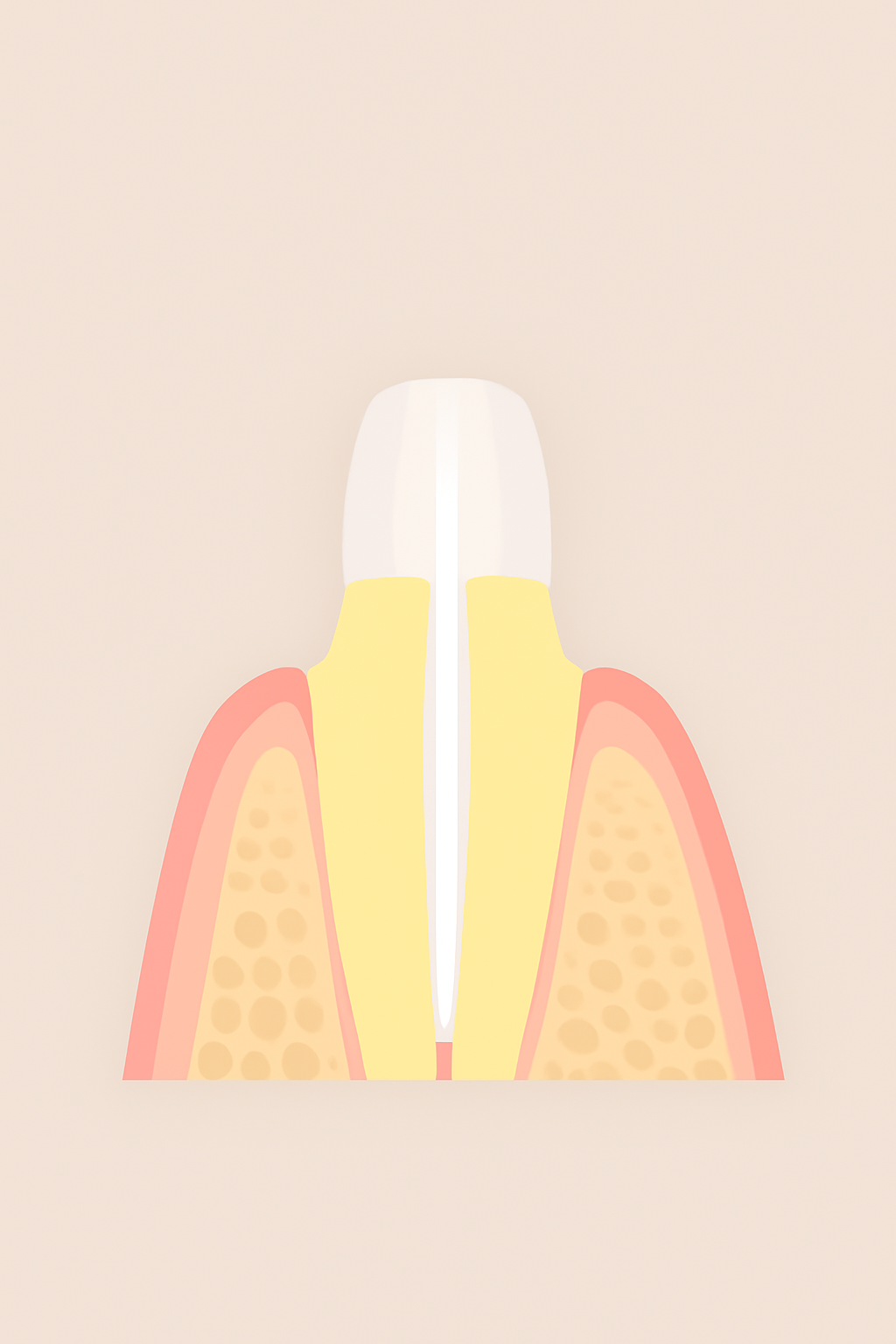2025年4月09日

(院長の徒然コラム)

はじめに
歯科診療において、抗生物質の使用は感染症の予防や治療に欠かせない重要な役割を果たしています。
歯周病治療や抜歯後の感染、その他外科手術や感染症など、様々な歯科治療の場面で抗生物質が処方されます。
しかし、その使用には適切な判断と注意が必要です。
本コラムでは、歯科で使用される抗生物質の種類と、その使用における注意点について詳しく解説します。
抗生物質とは
抗生物質は、細菌の増殖を抑制または殺菌する薬剤です。
これらは、細菌感染に対する治療薬として広く使用されており、歯科治療においても重要な役割を果たしています。
抗生物質は、細菌の細胞壁合成を阻害したり、タンパク質合成を妨げたりすることで、細菌の活動を抑制し、殺菌していきます。
歯科での使用目的
歯科診療での抗生物質の主な使用目的を列挙していきます。
①感染予防
抜歯などの外科手術などの観血的で侵襲的な処置の前後に感染を予防するために使用されます。
②既存の感染症の治療
歯周病や根尖性歯周炎などの治療において、感染を抑えるために処方されます。
特に急性症状がある場合は処方されるケースが多いです。
③術後感染の予防
手術後の二次感染を防ぐために、抗生物質が使用されることがあります。
一般的な歯科での抗生物質が出される適応症
歯科で抗生物質が処方される症状は様々です。以下で幾つか紹介いたします。
急性歯周炎
歯周病の急性発作に対して、感染を抑えるために使用されます。
顎骨周囲炎・歯槽骨炎
顎の骨や歯の周囲の骨に感染が広がった場合、抗生物質が必要です。
術後感染予防
手術後の感染を防ぐために、抗生物質が処方されることがあります。
根尖性歯周炎の急性発作
歯の根尖部に感染が生じた場合、抗生物質が必要です。
こういった症状に抗生物質は活用されているのです。抗生物質は血流に乗って作用するものなので、歯の内部などの細菌を倒す効果はありません。
歯科で使用される主な抗生物質の種類
歯科で使用される抗生物質の種類について紹介します。
ペニシリン系
①アモキシシリン
広域スペクトルを持ち、口腔内細菌に対して高い効果を示します。
成人には通常1回250mg〜500mgを1日3〜4回経口投与されます。商品名にはサワシリンやパセトシンがあります。
②アンピシリン
アモキシシリンと同様の効果を持ちますが、経口吸収率がやや劣ります。成人には通常1回250mg〜500mgを1日4回経口投与されます。商品名にはビクシリンがあります。
セフェム系
①セファレキシン
第一世代セフェム系で、グラム陽性菌に強い効果を示します。
成人には通常1回250mg〜500mgを1日4回経口投与されます。商品名にはケフレックスやラリキシンがあります。
②セフジニル
第三世代セフェム系で、より広範囲の細菌に効果を示します。成人には通常1回100mgを1日3回経口投与されます。商品名にはセフゾンがあります。
③セフジトレンピボキシル
第3世代のセフェム系抗生物質です。グラム陽性菌グラム陰性菌両方に効果を示します。
1回100mgを1日3回食後に経口投与します。商品名にはメイアクトなどがあります。
④セフカピペンピボキシル
第3世代のセフェム系抗生物質です。グラム陽性菌よりもグラム陰性菌の方に効果を示します。
1回100mgを1日3回食後に経口投与します。商品名にはフロモックスなどがあります。
マクロライド系
①アジスロマイシン
長時間作用型で、1日1回の投与で済みます。成人には500mgを1日1回、3日間経口投与されます。
商品名にはジスロマックがあります。
②クラリスロマイシン
広域スペクトルを持ち、組織移行性が高いです。
成人には1回200mgを1日2回経口投与されます。
商品名にはクラリスやクラリシッドがあります。
テトラサイクリン系
①ドキシサイクリン
歯周病原菌に対して効果が高く、抗炎症作用も持ちます。成人には1回100mgを1日1回経口投与されます。商品名にはビブラマイシンがあります。
②ミノサイクリン
組織移行性が高く、局所投与も可能です。
成人には1回100mgを1日2回経口投与されます。商品名にはミノマイシンがあります。
キノロン系ニューキノロン系
①レボフロキサシン
第三世代キノロン系で、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に効果があります。
成人には1回500mgを1日1回経口投与されます。商品名にはクラビットがあります。
歯科抗生物質の選択基準
歯科医師は、患者様に適切な抗生物質を選択する際に、以下の要因を考慮しています。是非参考に事前に患者様の情報を教えてくださると助かります。
①感染の種類と重症度
感染症の種類や重症度は、抗生物質の選択において重要な要因の一つです。
急性の感染症と慢性の感染症では、治療方針が異なります。
例えば、急性歯周炎や根尖性歯周炎などの急性の感染症には、迅速に効果を発揮する抗生物質が必要であり、投与期間や量も考慮されます。
一方、慢性の感染症では、長期的な治療が求められることがあります。
また、局所感染か全身感染かも考慮されます。(歯に感染した菌が全身に菌が回ることもあり得るのです。)
患者の年齢と全身状態
患者様の年齢や全身状態も、抗生物質の選択に影響を与えます。
小児や高齢者、妊婦、腎機能が低下している患者様には、特別な配慮が必要です。また錠剤の抗生物質が飲めない小児もいるでしょう。
錠剤か粉かを設定する必要があるのです。
その他にも例えば、小児には体重に応じた適切な用量を計算する必要がありますし、高齢者では腎機能が低下している場合が多いため、用量調整が必要です。
また、妊婦に対しては、胎児への影響を考慮し、安全性が確認されている抗生物質を選択することが求められます。
アレルギー歴
患者様のアレルギー歴も重要な要因です。
特にペニシリンアレルギーの有無は、抗生物質の選択に大きな影響を与えます。
ペニシリン系抗生物質は広く使用されていますが、アレルギーがある場合は、代替薬を選択する必要があります。
アレルギー反応は軽度のものから重篤なものまで様々であり、過去のアレルギー歴を正確に伝えることが重要です。
実際ペニシリンアレルギーで亡くなるケースもあるので注意が必要です。
薬剤耐性の考慮
抗生物質の使用においては、地域の耐性菌の傾向や患者様の抗生物質使用歴も考慮されます。
耐性菌は、抗生物質に対して抵抗力を持つ細菌であり、これが増殖すると治療が難しくなります。
地域によっては、特定の抗生物質に対する耐性が高まっている場合があるため、歯科医師は最新の情報を基に適切な薬剤を選択する必要があります。
抗生物質の適切な使用方法
抗生物質の効果を最大限に引き出すためには、以下のポイントを守ることが重要です。
①処方された通りの服用
抗生物質は、指示された用法・用量を厳守して服用することが基本です。
例えば、アモキシシリンの場合、成人には通常1回250mg〜500mgを1日3〜4回経口投与されます。
指示された通りに服用することで、血中濃度を適切に維持し、感染症に対する効果を最大化します。
②自己判断で薬を飲むのをやめない
症状が改善しても、処方された期間全てを服用することが重要です。
抗生物質を途中で中止すると、残存する細菌が耐性を持つ可能性があり、再発や重篤な感染を引き起こすリスクが高まります。
また、抗生物質は一定期間服用しないと血中の抗生物質濃度が上がっていきません。
抗生物質は数日間服用し続けることが一般的ですので、症状が改善したからといって自己判断で中止することは避けましょう。
③残薬の適切な処理
余った抗生物質は自己判断で使用せず、適切に処分することが求められます。
抗生物質の残薬を再度使用することは、耐性菌の発生を助長する可能性があるため危険です。
使用期限が過ぎた薬剤や、不要になった薬剤は、薬局や医療機関での適切な処分方法に従って処理することが重要です。
患者様へのアドバイス
抗生物質の選択には、ドクターの専門的な判断が不可欠です。
患者様は、自身の医療歴や服用中の薬剤について、歯科医師に正確に伝えることが重要になってきます。
歯科医院にかかる際には、お薬手帳を持参することを忘れないようにしましょう。
これにより、過去の治療歴や現在の服用薬を把握しやすくなり、より適切な治療を行うことができます。
また、抗生物質の服用について不明点があれば、必ず歯科医師や薬剤師に相談してください。特に、以下の点について確認することが大切です。
①アレルギー歴
ペニシリン系抗生物質などにアレルギーがある場合、他の抗生物質を選択する必要があります。
②薬剤服用歴
他の薬剤を服用している場合、相互作用があるかどうかを確認することが重要です。
③副作用
抗生物質には副作用があるため、異常を感じた場合はすぐに医療機関に相談することが必要です。
抗生物質使用の注意点
抗生物質の使用には、いくつかの注意点があります。
①副作用
抗生物質の使用には様々な副作用のリスクがあります。一般的な副作用としては、消化器症状(下痢、腹痛、嘔気など)が挙げられます。
これらの症状は、抗生物質が腸内の正常な細菌叢に影響を与えることによって引き起こされることがあります。
また、アレルギー反応(発疹、痒み、まれに重篤なアナフィラキシーショック)も注意が必要です。
これらの副作用が現れた場合は、すぐに歯科医師や医師に相談することが重要です。
②耐性菌の問題
抗生物質の不適切な使用は、耐性菌の発生を促進する可能性があります。
耐性菌は、抗生物質に対する耐性を持つ細菌が生き残り、増殖することによって発生します。これにより、通常の抗生物質では効果がない感染症が増加し、治療が難しくなります。
抗生物質を使用する際は、処方された用法・用量を守り、不必要な使用を避けることが重要です。
③相互作用
抗生物質は他の薬剤や食品と相互作用を起こす可能性があります。
例えば、テトラサイクリン系抗生物質は制酸剤や鉄剤と併用すると吸収が低下します。
また、一部の抗生物質はアルコールと併用すると副作用のリスクが高まるため、注意が必要です。
患者様は、服用中の他の薬剤や食品について歯科医師に相談し、相互作用のリスクを理解することが大切です。
終わりに
歯科における抗生物質の使用は、感染症の予防と治療に重要な役割を果たしています。しかし、その適切な使用には専門的な知識と慎重な判断が必要です。
患者様と歯科医師のコミュニケーションを通して、必要な情報を分析することで適切な抗生物質療法を行うことが出来るのです。ですので、効果的な治療と副作用のリスク低減のために、しっかりと薬剤や全身既往歴についてお尋ねしますので、どうぞご協力をお願いいたします。
もし抗生物質に関する疑問や不安がある場合は、躊躇せずにご相談なさってください。正しい情報と適切な指導を受けることで、より安全で効果的な治療を受けることができます。
患者様の健康を守るために、抗生物質の正しい使用を心がけましょう。