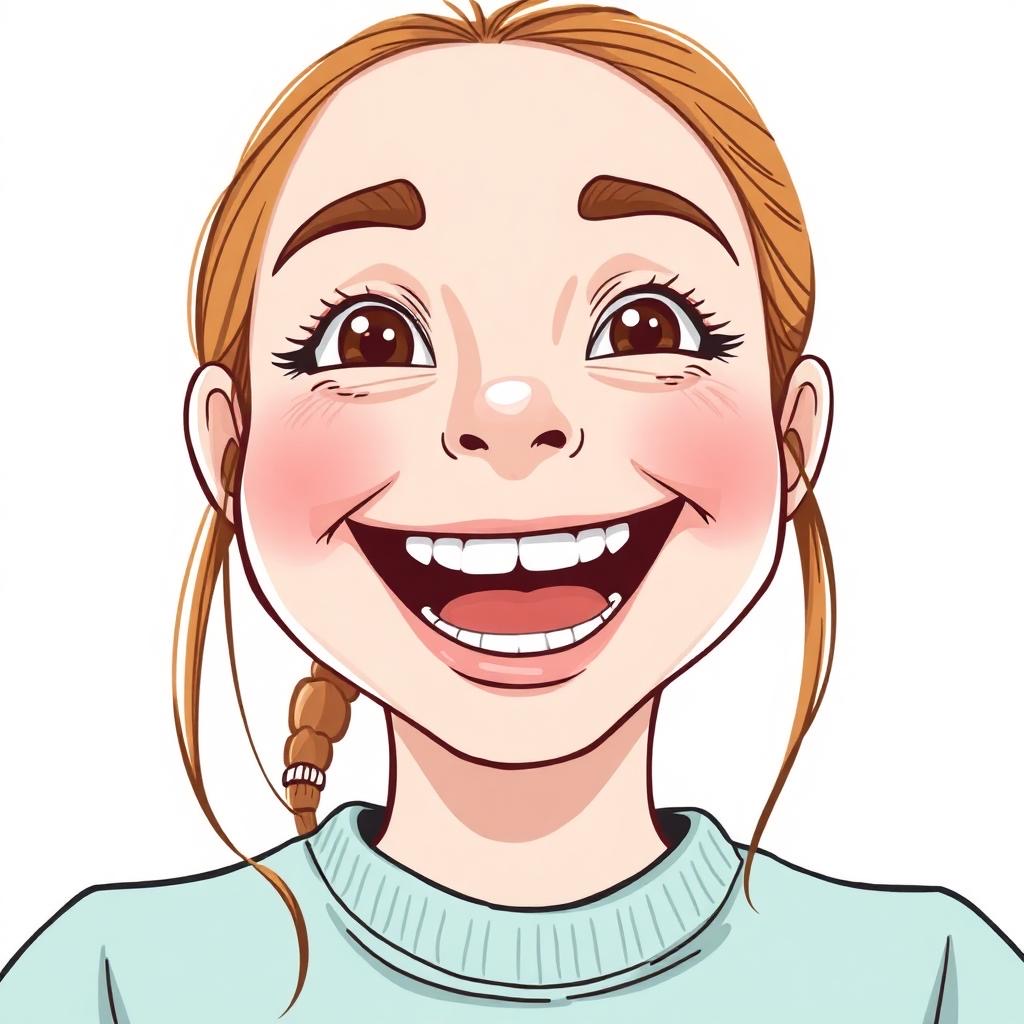2025年1月15日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
皆さんは親知らずなど、歯を抜いたことはありますか?
歯を抜いた後の穴、傷のことを抜歯窩と呼びます。
抜歯は、歯科治療において一般的な手技の一つであり、さまざまな理由から行われます。
抜歯後の創傷治癒は、患者の回復やその後の治療に大きな影響を与えるため、理解しておくことが重要です。
時に抜歯後に痛みがすぐ引かなくて不安になったり、全身疾患の兼ね合いで治りに対して不安に思うこともあると思います。
本コラムでは、抜歯窩の創傷治癒の経過について詳しく解説します。
抜歯の目的とその影響
抜歯は、虫歯、歯周病、過剰歯、矯正治療の一環など、さまざまな理由で行われます。
先ほど説明した通り、抜歯後、歯が失われた部位には「抜歯窩」と呼ばれる空間が形成されます。
この抜歯窩は、創傷治癒の過程を経て、最終的には骨や血管、繊維組織などの軟組織が再生されることになります。
創傷治癒の過程
それでは、抜歯窩がどのようにどれくらいの期間をかけて治っていくのかを説明していきます。
抜歯窩の創傷治癒は、主に以下の4つの段階に分けられます。
①炎症期(1〜3日)
抜歯直後、抜歯窩には出血が見られます。この出血は、血小板が集まり、血栓を形成することで止まります。
血栓は、創傷部位を保護し、感染を防ぐ役割を果たします。
この段階では、炎症反応が起こり、白血球が傷口に集まってきます。
これにより、マクロファージなどにより貪食されて細菌や異物が排除され、創傷の清浄化が進みます。
②増殖期(3日〜2週間)
炎症期が終わると、増殖期に入ります。
この段階では、血栓が徐々に分解され、繊維芽細胞が増殖し、再生の足場となるコラーゲンが合成されます。これにより、抜歯窩の内側に新しい組織が形成され、肉芽組織が発達します。
肉芽組織は、血管が豊富で、創傷の修復に重要な役割を果たします。つまり傷の内部に血管新生されるのです。
この時期には、痛みや腫れが続くことがありますが、通常は徐々に軽減していきます。
また、抜歯窩の周囲の組織も回復し始め、正常な組織に戻る準備が整います。
③再生期(2週間〜数ヶ月)
増殖期が進むと、再生期に入ります。この段階では、肉芽組織が成熟し、血管が減少していきます。
コラーゲンがより組織化され、創傷時の強度が増していきます。抜歯窩の形状も徐々に整い、周囲の骨と結合していきます。
この時期には、抜歯窩の痛みや腫れはほとんどなくなり、患者は通常の生活に戻ることができます。
この再生期は、上顎では6ヶ月、下顎では3ヶ月程度とされております。
④完成期(数ヶ月〜1年)
再生期が終わると、完成期に入ります。
この段階では、抜歯窩の骨が再生され、周囲の組織と完全に統合されます。レントゲン画像でプロが見ないと判別できないほど綺麗に治っていきます。
骨の再生は、通常数ヶ月から1年かかることがあります。この時期には、抜歯窩の形状が安定し、周囲の歯や組織に馴染んで調和が取れるようになります。
創傷治癒に影響を与える要因
抜歯窩の創傷治癒には、さまざまな要因が影響を与えます。ここでは主な要因を幾つか挙げます。
①患者の全身状態
患者の全身状態は、創傷治癒に大きな影響を与えます。
例えば糖尿病や免疫不全などの疾患を持つ患者は、免疫力が低下しているため感染リスクが高く、創傷治癒が遅れることがあります。
また、喫煙も血流を悪化させ、創傷治癒を妨げる要因となります。
②抜歯の技術・手法
抜歯の技術や手法も、創傷治癒に影響を与えます。適切な手技で抜歯が行われると、周囲の組織へのダメージが少なく、創傷治癒がスムーズに進むことが期待できます。
手技が適切であっても、やむを得ない骨削除が必要な場合は、治りが遅くなることもあります。
さらに、血餅が十分に出来ない状態で手技を終えたり、強いうがいや機械的刺激により血餅が剥がれたりすることも治癒に影響します。
③抜歯後の衛生状態
抜歯後の口腔内の衛生状態も重要です。
感染が起こると、炎症が悪化し、創傷治癒が遅れることがあります。
患者には、抜歯後の口腔ケアや食事に関する指導が必要です。
予め抜歯前にクリーニングや患者さんのプラークコントロールの改善をを済ませておき、感染リスクを下げることも重要です。
抜歯後のケアと注意点
抜歯後のケアは、創傷治癒を促進するために非常に重要です。患者が注意すべきポイントを下記で詳しく説明いたします。
①出血の管理
抜歯後は、出血が見られることがあります。
出血が続く場合は、清潔なガーゼを噛むことで圧迫止血を行います。
出血が止まらない場合は、専用の止血剤や縫合で対処することもあります。
②食事の注意
抜歯後は、硬い食べ物や熱い飲み物を避け、柔らかい食事を摂ることが推奨されます。
辛いものなどの刺激物も避けて、あまり噛まなくてもいい食べ物を選びましょう
また、抜歯窩に直接触れないように注意し、口腔内の衛生状態を保つことが大切です。
できるだけ抜いた歯の方とは反対側で噛むようにして、刺激を与えないようにしましょう。
④抜歯後の診察
抜歯後は、直後に消毒、縫合した場合は1から2週間を目処に抜糸など歯科医師の診察を受けることが重要です。
創傷の治癒状況を確認し、必要に応じて適切な処置を行うことで、合併症を防ぐことができます。
⑤薬の処方
アレルギーやすでに飲んでいるお薬があるなどの事情ない限り、ほとんどの場合抜歯後は薬を処方されます。
指定された用法容量を守り、服用されてください。
抗生物質は抜歯窩の二次感染を防ぎ、鎮痛剤は痛みを抑えてくれます。
場合によっては、胃薬なども同時に処方されることがあります。
必ず飲み忘れのないようにしましょう。
終わりに
いかがでしたか。抜歯治療を受ける時も不安になりますが、傷の腫れや骨の治りも同じくらい不安になることがあるかと思います。
歯科医院では抜歯後も、しっかりと状態を診て、適切な治療を行いますので、不安になることがございましたらお気軽にご相談ください。