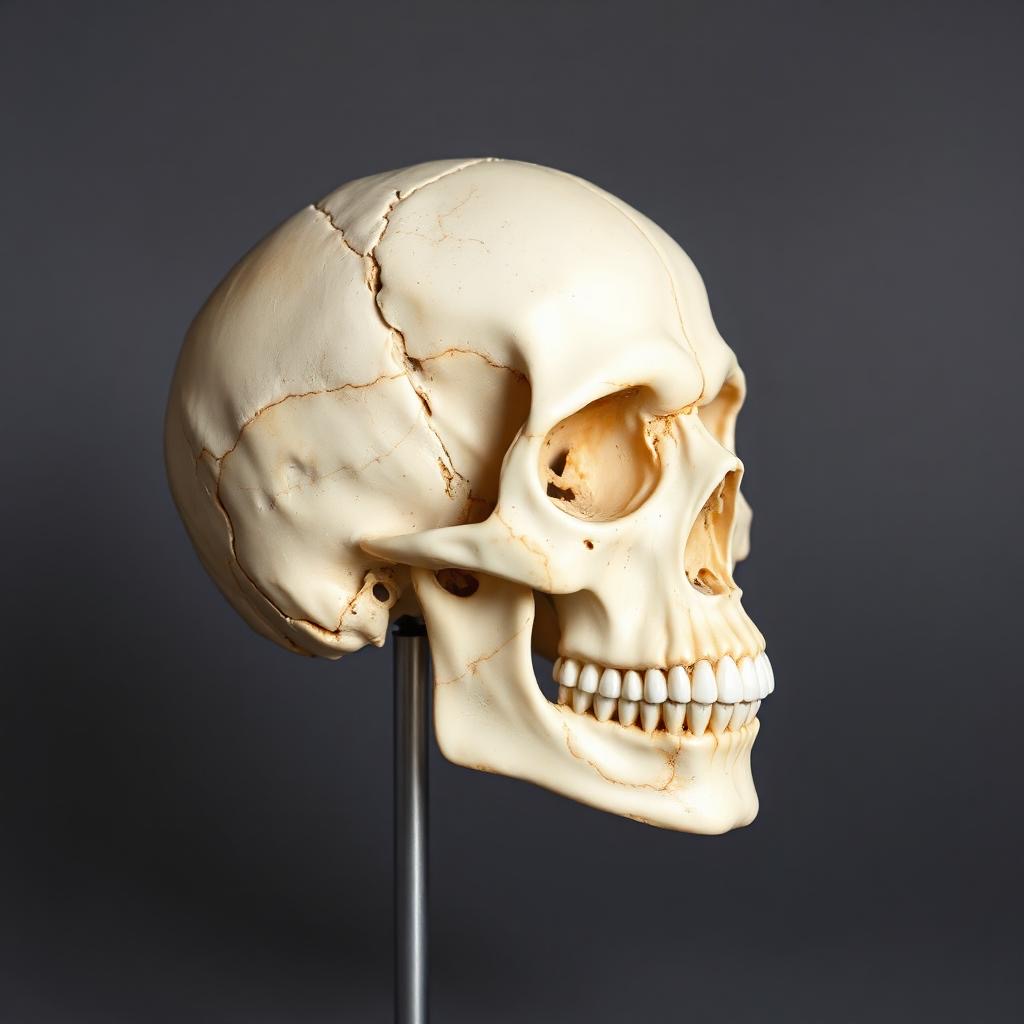2024年12月11日

(院長の徒然ブログ)

歯肉増殖症について
歯肉増殖症(gingival hyperplasia)は、歯肉組織の異常な「増殖」を特徴とする病態であり、主に歯肉の「腫脹」や「肥厚」を引き起こします。
これは一般的な歯周病のように、感染で膿が溜まって腫れ上がっているのではなく、歯茎の上皮下にある線維性組織が異常な増殖をしているために起こります。
この病態は、お口の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、特に歯周病を悪化させ、口腔衛生に関連する問題を引き起こすことがあります。
今回のコラムでは、歯肉増殖症の原因となる薬剤、病態生理、診断方法、治療法について詳述します。
歯肉増殖症の種類
⚫︎単純性歯肉増殖症
口呼吸などによる口腔内の乾燥、その他生活などによる刺激が原因で辺縁歯肉に発症する歯肉増殖です。
⚫︎歯肉繊維種症
腫れたという感じがあまり無く、炎症を伴わない上下歯肉全体の増殖により、歯が歯肉に覆われることもある歯肉増殖。
⚫︎薬物誘発性紙肉肥厚
後述の薬物によって引き起こされる薬物誘発性の歯肉増殖です。
歯肉増殖症の病態生理
歯肉増殖症は、主に歯肉の線維性組織の過剰な増殖によって引き起こされます。この病態は、細胞の増殖とアポトーシスの不均衡によって生じると考えられています。
特に、なんらかの原因での線維芽細胞の異常な活性化が重要な役割を果たしており、これによりコラーゲン合成が促進され、歯肉組織が肥厚します。
原因となる薬剤
歯肉増殖症は、いくつかの薬剤によって引き起こされることが知られています。以下に代表的な薬剤を挙げます。
1.抗てんかん薬
フェニトインやカルバマゼピン、アレビアチン、ジフェニルヒダントインなどの抗てんかん薬は、歯肉増殖症を引き起こすとされています。
これらの薬剤は、歯肉の線維芽細胞に対して直接的な刺激を与え、過剰なコラーゲン合成を引き起こします。
長期服用で半分くらいの患者さんが歯肉増殖を起こします。
2.高血圧治療薬(降圧剤)
高血圧症、狭心症の治療薬の中のカルシウム拮抗薬であるニフェジピン(アダラート)、ベラパミル(ワソラン)、ジルチアゼム(ヘルベッサー)、ニカルジピン(ペルジピン)などの薬も歯肉増殖を引き起こすことがあります。
場合によっては、別の種類の薬に変更する必要もあります。
約2割の患者さんで歯肉増殖を起こします。
3.免疫抑制剤
シクロスポリンA(cyclosporine)などの免疫抑制剤も、歯肉増殖症を引き起こすことがあります。
これらの薬剤は、免疫系の抑制により、歯肉組織の炎症反応を変化させ、結果として組織の過剰な増殖を促進します。
約3割の患者さんで歯肉増殖が引き起こされます。
4.ホルモン剤
妊娠中や経口避妊薬の使用に伴うホルモン変動も、歯肉増殖症の発症に寄与することがあります。特にエストロゲン(estrogen)の影響が大きいとされています。
診断方法
歯肉増殖症の診断は、主に臨床的な評価に基づいて行われます。
クリニックでは、患者の病歴や服用中の薬剤を確認し、視診および触診を通じて歯肉の状態を評価します。
必要に応じて、以下の検査が行われることがあります。
生検
歯肉組織の一部を採取し、病理学的に評価することで、他の病態との鑑別が可能です。
前述の通り、線維芽細胞の活性化によって起こるため、病理検査では歯肉上皮下での線維芽細胞の増殖像がみられる。
血液検査
稀にですが、全身的な健康状態や、他の疾患の有無を確認するために行われることがあります。
治療法
歯肉増殖症の治療は、原因に応じて異なります。以下に一般的な治療法を示します。
1. 薬剤の見直し
歯肉増殖症の原因となっている薬剤が特定された場合、医師と相談の上で薬剤の変更や減量を検討することが重要です。
ただし、抗てんかん薬など変更できない場合もあります。
2. 口腔衛生の改善
歯肉の健康を維持するためには、適切な口腔衛生が不可欠です。定期的な歯磨きやフロスの使用、歯科医師によるクリーニングが推奨されます。
ただプラークコントロールが良好であれば歯肉増殖は抑えられると言われていますが、増殖した歯肉が邪魔をし、中々改善しない事例も多いです。
3. 外科的治療
重度の歯肉増殖症の場合、外科的な介入が必要となることがあります。
歯肉切除術や歯肉形成術などが行われ、過剰な組織を除去することで、機能的および審美的な改善が図られます。
最近ではレーザーを使って行う方が多いですね。
増殖した部分のみを焼き切って収縮させます。
4. 定期的なフォローアップ
治療後も定期的なフォローアップが重要です。再発を防ぐために、口腔衛生の維持や、必要に応じた治療を継続することが求められます。
終わりに
歯肉増殖症は、さまざまな要因によって引き起こされる口腔内の病態であり、特に薬剤の影響が大きいことがわかっています。
適切な治療、そしてお口の健康を守るために、薬剤情報や全身状態をしっかりと歯科医院側が把握しておく必要があります、密なコミュニケーションを通じて、最適な治療法を見つけていきましょう。