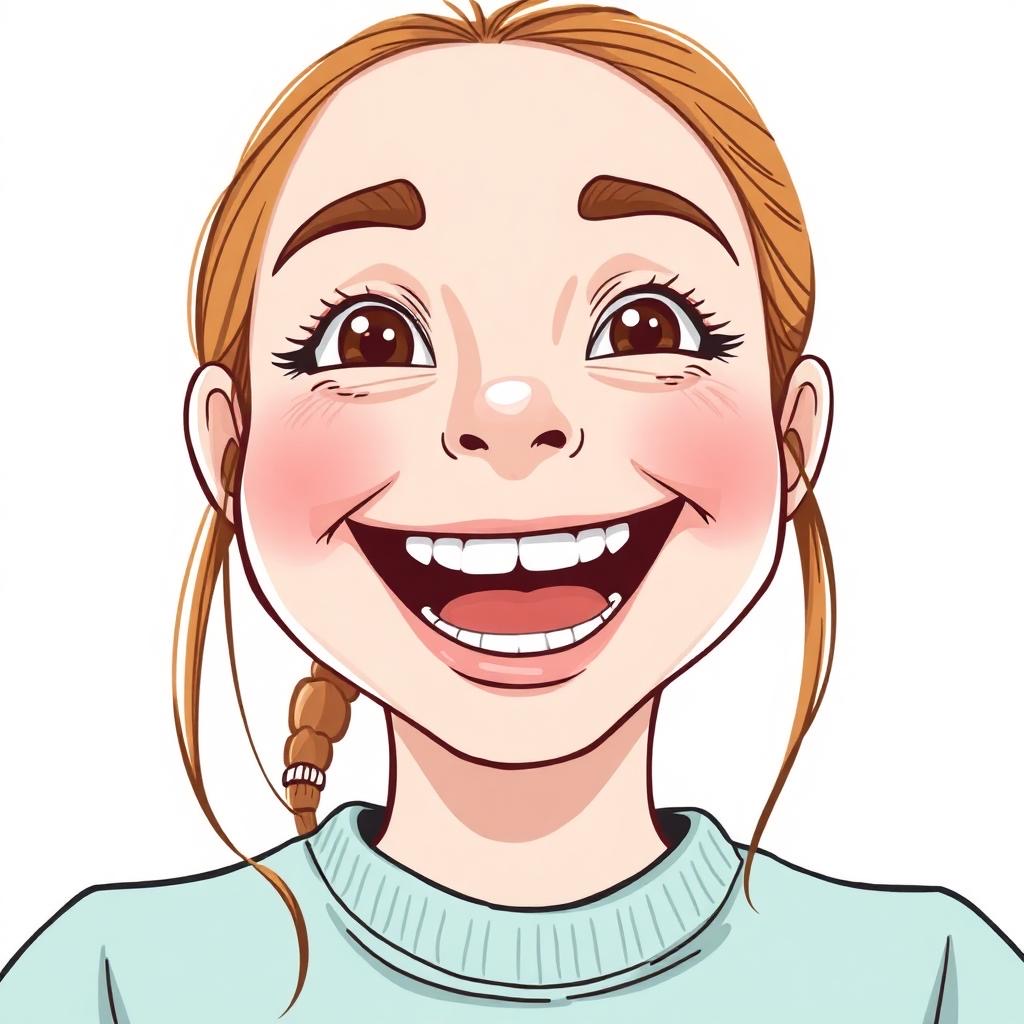2025年4月05日

(院長の徒然ブログ)

はじめに
粘液嚢胞は、口腔内や唾液腺に発生する良性の腫瘍であり、特に下唇の内側や舌下、頬の内側や稀に上顎に見られます。
これらの嚢胞は、粘液が貯留することによって形成され、通常は無痛性であるため、患者が気づかないこともあります。
しかし、粘液嚢胞は時に大きくなり、周囲の組織に影響を及ぼすことがあります。
今回のコラムでは、粘液嚢胞の定義、症状、好発部位、原因、治療法について詳しく解説します。
粘液嚢胞とは
粘液嚢胞は、唾液腺から分泌される粘液が貯留することによって形成される嚢胞です。
(要するに中に詰まっているのは唾液です。)
通常、唾液腺の導管が閉塞されることによって発生し、内部には粘液が充満しています。
粘液嚢胞は、一般的に良性であり、悪性腫瘍に進展することはありませんが、外見上の問題や舌感、機能的な障害を引き起こすことがあります。
粘液嚢胞の症状
粘液嚢胞の主な症状は、口腔内に発生する無痛性の腫瘤です。
嚢胞は通常、柔らかく、弾力性があり、色は深在性のものは周囲の粘膜と同じで、浅在性のものは透明感のある紫青色をしていることが多いです。
大きさは5mm前後から数cmまで様々で、嚢胞が大きくなると、周囲の組織に圧迫感を与えることがあります。
また、嚢胞が破裂すると、粘液が口腔内に漏れ出し、一時的に症状が改善することもありますが、その後再発することが多いです。
粘液嚢胞の好発部位
粘液嚢胞は、主に以下の部位に好発します。
①下唇
最も一般的な発生部位であり、外的な刺激や損傷が原因となることが多いです。
これは下唇の内側には小唾液腺が多くあるためです。
ほとんどのケースで左右のどちらかに寄っており、正中には滅多にできません。
②舌
舌の側面や裏側に発生することがあります。
ここにも小唾液腺が多くあります。
③頬の内側
頬の粘膜に発生することもあり、特に頬の内側の唾液腺に関連しています。
④口蓋
まれに口蓋に発生することもありますが、他と比べると小唾液腺の密度は低く、他の部位に比べると少ないです。
粘液嚢胞の原因
粘液嚢胞の主な原因は、唾液腺の導管の閉塞です。口腔内の唾液腺は、3つの主要な大唾液腺と、それ以外の多くの小唾液腺に分類されています。
大唾液腺には耳下腺、顎下腺、舌下腺の3つがあり、小唾液腺は唇の裏側や頬の内側などの口腔粘膜に存在します。
その小唾液腺からは細い導管が出ており、管を通じて唾液が口腔内に分泌されているのです。
この小唾液腺から出ている管がなんらかの理由で損傷すると、導管が閉塞し、唾液が粘膜の下に貯留してしまうことあるのです。
これには以下のような要因が関与しています。
①外的な損傷
口腔内の外的な刺激や損傷(例えば、噛み傷や外傷)が導管を閉塞することがあります。
特に下唇、舌、頬の内側はこのケースが多いです。
歯並びが悪い方などは、同じ場所を噛んでしまうことが多く、リスクが高くなってしまいます。
②慢性的な炎症
唾液腺の慢性的な炎症(例えば、唾液腺炎)が導管の狭窄を引き起こし、粘液の貯留を惹起してしまうことがあります。
口内炎などでも、内部の小唾液腺を傷つけて粘液嚢胞になってしまう場合があります。
③唾液腺の異常
一部の患者では、先天的な唾液腺の異常が原因で粘液嚢胞が発生することがあります。
その場合も唾液腺自体や導管閉塞によって粘液嚢胞を引き起こす場合があります。
粘液嚢胞の治療法
粘液嚢胞の治療法は、嚢胞の大きさや場所、症状に応じて異なります。以下に主な治療法を示します。
①経過観察
小さく無症状の粘液嚢胞は、処置しない場合もあります。基本的に良性なので、特に治療を必要としない場合があります。
その場合は定期的な観察を行い、変化がないか確認します。
ただし、殆どの粘液嚢胞は潰れても再発するケースが多いです。
②外科的切除
嚢胞が大きくなったり、症状を引き起こす場合は、外科的に切除することが推奨されます。
切除は、嚢胞の根元まで行うことが重要で、再発を防ぐためには完全な摘出が必要です。
手術は、局所麻酔で粘膜を切開し、嚢胞を残さず摘出していくのですが、その際に嚢胞付近にある、小唾液腺も同時に摘出することが一般的です。
その後切開部を縫合します。
通常は1週間程度で抜糸を行います。
手術の所要時間は短く、15分も掛かりません。
一般的に創も小さく傷口から多少の出血が見られるものの、痛みは殆どありません
ちなみに唾液の95%は大唾液腺から分泌されるため、小唾液腺を一つとったところで影響は出ません。
③レーザー治療法
最近は殆どレーザー治療が主流です。
局所麻酔を患部周囲に行ってからレーザーで蒸散させつつ摘出していきます。
手術後の出血や痛みがとても少なく、縫合の必要もありません。
レーザーを当てて治療すると、患部周囲の細胞の新陳代謝が活性化され、自己治癒力が向上する他、炎症部分の接触時の痛みが軽減されます。
おまけに平面を均一に蒸散させることで、治癒が早く傷も少なくなります。
またベイルビー層という皮膜が創面にでき、炎症部分の接触時に起こる痛みが軽減され、治りが早くなります。
場所による粘液嚢胞の名称の違い
①がま腫
大唾液腺の一つである舌下腺の損傷によって起こり、口底に出来るものを特に「がま種」と呼びます。
因みに舌下腺の口腔内への開口部は顎下腺の管と合流する大舌下腺管(バルトリン管)と舌下ヒダに開口する小舌下腺管(リビナス管)があり、導管閉塞でもがま腫になります。
②BlandinNuhn嚢胞
舌の先端の下部(舌の裏側)にできる粘液嚢胞で、比較的好発する嚢胞です。これは前舌腺に由来するものであり、特にBlandinNuhn嚢胞とよばれています。
終わりに
粘液嚢胞は、口腔内で一般的に見られる良性の腫瘍ですが、外見上の問題や機能的な障害を引き起こすことがあります。
早期の診断と適切な治療が重要であり、特に外科的切除が必要な場合は、歯科医院にて診察が必要となります。
口腔内の健康を維持するためには、定期的な歯科検診を受け、異常を早期に発見することが大切です。
粘液嚢胞についての理解を深め、適切な対処を行うことで、健康な口腔環境を保つことができるでしょう。