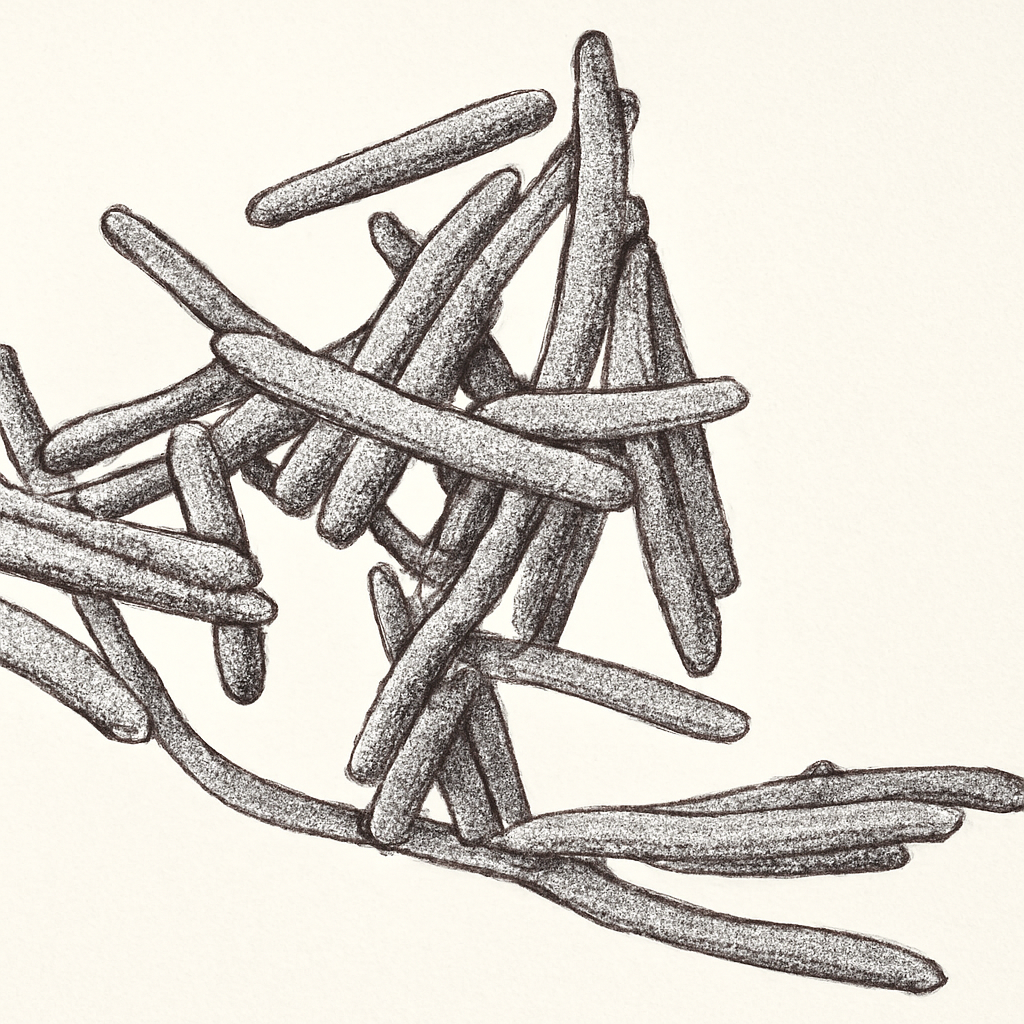2025年1月27日

「歯が削れている気がする」「歯の形が変わってきた」というお悩みを抱えていませんか?歯は毎日の食事や噛みしめなどで徐々にすり減っていきますが、原因によっては早い段階で大きなダメージを受けてしまうこともあります。今回は、歯のすり減りの原因と対策についてわかりやすくお伝えします。
歯のすり減りの主な原因
1. 加齢による自然な摩耗
歯は食べ物を噛むたびに少しずつ摩耗します。これ自体は自然な現象で、特に大きな問題にはなりません。ただし、歯ぎしりや不正な噛み合わせがあると、摩耗が早く進むことがあります。
2. 歯ぎしり・食いしばり
無意識のうちに強い力で歯を擦り合わせる歯ぎしりや、強く噛みしめる食いしばりは、歯に大きな負担をかけます。このような癖があると、エナメル質(歯の表面)が急速に削れ、歯が短くなったり、噛み合わせが変化したりすることがあります。
3. 硬い食べ物や酸性食品の影響
硬い食べ物(ナッツ、硬いお菓子など)を頻繁に食べると、歯に強い圧力がかかり、すり減りやすくなります。また、酸性食品(炭酸飲料、レモン、酢など)を多く摂取すると、歯の表面が酸により溶けやすくなり、摩耗が進行します。
4. 歯ブラシの力が強すぎる
歯を強く磨きすぎると、歯の表面が傷つき、徐々に削れてしまいます。特に硬めの歯ブラシや横磨きの癖がある方は注意が必要です。
5. 酸蝕症(エナメル質が溶ける状態)
胃酸の逆流や、酸性の飲食物を頻繁に摂取することで、歯のエナメル質が溶けることがあります。この状態が続くと、歯が柔らかくなり、さらに摩耗しやすくなります。
歯のすり減りを防ぐための対策
1. 噛み合わせや歯ぎしりのチェック
歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、歯科医院で作成するナイトガード(マウスピース)を使用すると、歯を保護できます。
2. 柔らかめの歯ブラシで優しく磨く
強い力で磨かないように気をつけ、歯に優しい柔らかめの歯ブラシを使いましょう。
3. 酸性の飲食物を控える
炭酸飲料や柑橘類を摂取した後は、水で口をすすぐなどのケアを心がけ、歯の表面が溶けるのを防ぎます。
4. 定期的な歯科検診
歯のすり減りの進行度を確認し、早めに対策を講じることが大切です。特に噛み合わせのチェックや予防ケアを受けることで、摩耗を最小限に抑えられます。

歯のすり減りは自然な現象ですが、原因によっては予防や改善が可能です。放置すると知覚過敏や歯の形状の変化、噛み合わせの異常につながることもありますので、気になる症状がある場合は早めにご相談ください。
当院では、歯の健康を守るための予防ケアや専門的な治療を行っています。ぜひお気軽にお越しください!