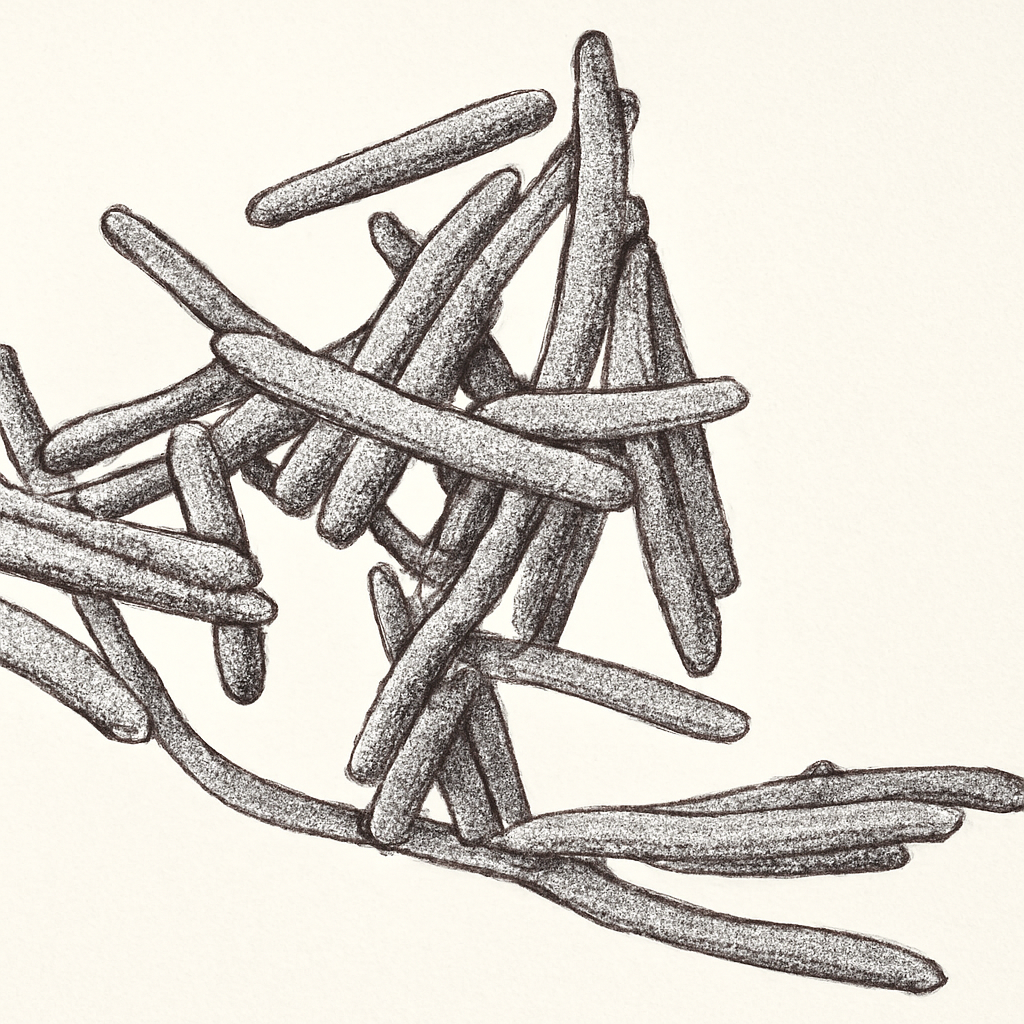2024年12月03日

(院長の徒然ブログ)

亜鉛欠乏症について
亜鉛は、体内で多くの重要な機能を果たす必須ミネラルです。
特に、免疫機能、細胞分裂、創傷治癒、そして味覚において重要な役割を果たしています。
亜鉛が不足すると、味覚障害が生じることがあり、これは食事の楽しみを損なうだけでなく、栄養摂取にも影響を与える可能性があります。
しかも亜鉛は筋肉や骨や多くの臓器に含まれているのですが、体内生成はできず、食事による摂取しか補給方法がありません。
「日本人の食事摂取基準2020年」によると、成人の1日の亜鉛推奨摂取量は、男性は10-11mg、女性8mgとなっています。
しかし、日本人の亜鉛の平均摂取量は男女とも下回っています。
因みに定義として、血液中の亜鉛濃度の基準値は80-130μg/dlで、60-80μg/dl未満は潜在性亜鉛欠乏であり、60μg/dl未満が亜鉛欠乏症となっており、加齢に伴って血清亜鉛濃度が低下する傾向にあります。
順天堂大学の研究によると、男性の約半数近く、女性の約4割が潜在性亜鉛欠乏の状態だそうです。
今回は、そんな亜鉛の欠乏による味覚障害のメカニズム、症状、診断、治療法、そして亜鉛を多く含む食材について詳しく解説していきます。
亜鉛の役割
亜鉛は、体内で300以上の酵素の構成要素として機能し、タンパク質合成やDNA合成に関与しています。
また、亜鉛は味覚を司る味蕾の正常な機能にも不可欠です。味蕾は舌の表面に存在し、食べ物の味を感知する役割を果たしています。
亜鉛が不足すると、味蕾の細胞が正常に機能せず、味覚が鈍化したり、異常な味を感じたりすることがあります。
その他にも亜鉛欠乏症だと、疲労感が取れない、食欲不振や下痢、免疫力の低下、生殖機能の低下、貧血、骨粗しょう症、皮膚炎や脱毛、小児の身長•体重の増加不良などの症状が出てきます。
一説ではストレスにも関与しており、亜鉛欠乏により精神面の不調も出てくるそうです。
亜鉛欠乏による味覚障害のメカニズム
では、亜鉛欠乏が味覚に与える影響と、そのメカニズムについて説明していきます。
①味蕾の機能低下
前述の通り亜鉛は細胞分裂にも関わっているため、味蕾の細胞の成長と再生に必要です。
亜鉛が不足すると、味蕾の細胞が正常に再生されず、味覚が低下します。
②神経伝達の障害
亜鉛は神経伝達物質の合成にも関与しています。
亜鉛が不足すると、味覚信号が脳に正しく伝わらず、味覚の感知が鈍くなります。
③免疫機能の低下
亜鉛は免疫系にも重要な役割を果たしています。
亜鉛が不足すると、口腔内の感染症や炎症が起こりやすくなり、これが味覚に影響を与えることがあります。
亜鉛欠乏による味覚障害の症状
亜鉛欠乏による味覚障害の主な症状には以下のようなものがあります。
⚫︎味覚の鈍化
味蕾細胞の再生異常により食べ物の味が感じにくくなる。
⚫︎異常味覚
甘味や塩味が感じられず、苦味や酸味が強く感じられることがある。
⚫︎食欲不振
味覚の変化により、食事が楽しめなくなり、食欲が減退して食事量が低下する。
⚫︎口内の異常感
口の中が乾燥したり、金属的な味を感じることがある。
亜鉛欠乏の診断
亜鉛欠乏の診断は、主に以下のような方法で行われます。
①血液検査
血中の亜鉛濃度を測定することで、亜鉛欠乏の有無を確認します。
基準については前述のとおりです。
②症状の評価
味覚障害の症状や食事内容を評価し、亜鉛不足の可能性を考慮します。
③食事調査
実際の食事内容を調査し、亜鉛の摂取量を計算して確認します。
亜鉛欠乏症への対応
それでは亜鉛欠乏の治療について説明してまいります。
①亜鉛サプリメント
亜鉛サプリメントを摂取することで、亜鉛不足を補います。
②食事改善
亜鉛を多く含む食材を積極的に摂取することが重要です。後ほど亜鉛が豊富な食材について詳しく説明していきます。
③薬物治療療法
食事療法だけで改善しない場合や、重度の亜鉛欠乏の場合は酢酸亜鉛水和物、ヒスチジン亜鉛水和物製剤などによる薬物治療を検討します。
亜鉛が多く含まれる食材
ここでは亜鉛を豊富に含む食材を紹介しておきます。
しかし、亜鉛を取るのも大事ですが、亜鉛の吸収を助ける食事、例えば肉や魚に含まれる動物性タンパク質、ビタミンC、クエン酸などの亜鉛の吸収を促進する食材も同時に食べてください。
反対に小麦などの穀類、コーヒー、オレンジジュースなどは亜鉛の吸収を阻害してしまいます。
①肉類
牛肉、豚肉、鶏肉などの赤身肉は亜鉛の良い供給源です。特に、牛肉の赤身部分には多くの亜鉛が含まれています。
また、レバーもおすすめです。
②魚介類
特にカキは亜鉛含有量が非常に高いことで知られています。その他にも、エビやイカなどの魚介類も良い選択肢です。
③ナッツ類
アーモンドやカシューナッツ、ピスタチオなどのナッツ類も亜鉛を含んでいます。
おやつとして手軽に摂取できるのが魅力です。
④豆類
レンズ豆やひよこ豆、大豆などの豆類も亜鉛を含んでいます。特に、ビーガンやベジタリアンの方にとっては重要な亜鉛源となります。
⑤全粒穀物
オートミールや全粒パン、玄米などの全粒穀物も亜鉛を含んでいます。精製された穀物よりも栄養価が高いです。
⑥乳製品
チーズやヨーグルトなどの乳製品も亜鉛を含んでいます。特にチーズは、亜鉛の良い供給源です。
終わりに
亜鉛は、味覚を含む多くの生理的機能において重要な役割を果たしています。
亜鉛欠乏による味覚障害は、食事の楽しみを損なうだけでなく、栄養摂取にも影響を与える可能性があります。
皆さんも普段から亜鉛を多く含む食材を意識的に摂取していきましょう。